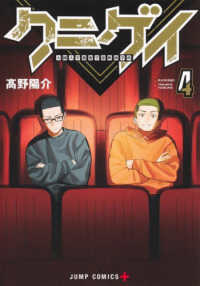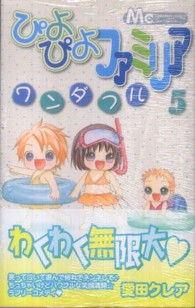内容説明
『菊と刀』から「日本叩き、日本封じ込め」論まで、日本「独自性」神話をも創り出した。その議論の移り変りを、戦後の流れのなかで捉え直した力作。吉野作造賞受賞のロングセラー。
目次
1 戦後日本と「日本文化論」の変容
2 『菊と刀』の性格
3 「否定的特殊性の認識」(1945~54)
4 「歴史的相対性の認識」(1955~63)
5 「肯定的特殊性の認識」前期(1964~76)、後期(1977~83)
6 「特殊から普遍へ」(1984~)
7 「国際化」の中の「日本文化論」
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Shin
16
いわゆる「日本人論」、米国留学の際にアイデンティティ・クライシスに陥ったのをきっかけに、いろいろと読んでみたのが12年ほど前。それ以来、本棚の一角を占める「日本人論コーナー」になっているのだけど、先日ふとしたきっかけで船曳建夫『「日本人論」再考』を再読し、改めて令和の時代のいま、日本人論を振り返るのも価値があるだろうと思い、読めていなかった本書を手に取った。あまりにも有名な『菊と刀』をキーブックとして、否定と肯定、絶対化と相対化、個別化と普遍化という対立軸から戦後の日本人論の変遷を読み解く。2020/12/20
さえきかずひこ
2
『菊と刀』以降の日本文化論という言説を、時代や社会の変化と合わせてとらえて分析する一冊。簡明で無駄のない文体で読みやすく、それでいて読みごたえはどっしりしている。良い本です。2016/10/19
nonnomarukari(ノンノ〇(仮))
2
「日本人論」再考と同じ趣旨で日本人論に対する疑問を持って読んで見た一冊。これは再考とは違う点は再考は明治時代から戦前のものもあったが、変容は戦後から平成時代までのものを詳しく集めている。加藤周一の雑種の文化という視点は面白かったので今度また彼の著作を読んでみようとしたい。2011/01/24
たろーたん
1
日本文化論でまず出てくるのはルース・ベネディクト『菊と刀』だ。日本人の特殊性が否定的に描かれていく。しかし、50年代後半になると、むしろ日本人の特殊性が肯定的に描かれていく。加藤周一「日本文化の雑種性」、梅棹忠雄「生態史観(アジアとヨーロッパを違う文明と位置づけ、日本は西洋に劣っているのではなく、西欧とは違うアジアとして見るべき)」が現れる。また1960年代後半になると、中根千枝「日本の集団主義、場の意識(タテ社会ってタイトルだけど、こちらの方が本質)」、(続)2023/05/28
kukikeikou
1
はじめての青木保。戦後日本人論の丁寧な概観。否定的特殊性の時代、歴史相対性の時代、肯定的特殊性の時代、普遍主義へ、と90年までを四期に区分する。解説にあるように、この本がバブルただ中に出されたことで、その後の日本人の自己認識について触れ得なかったことは惜しいし、更には現在のナルシシズムとナショナリズムに立脚する日本ブームについても同様の観点から淡々と比較してみてもらいたいところ。何れにせよどのような立場の人もこの本は読むべし、そう思える本2017/02/28
-
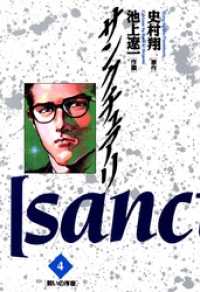
- 電子書籍
- サンクチュアリ(4) ビッグコミックス
-

- 和書
- 道 - たびびと日記