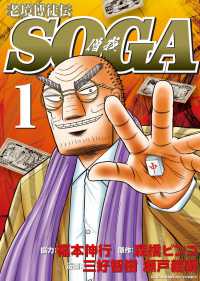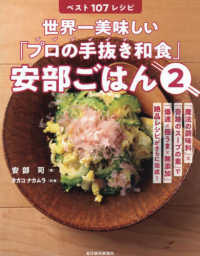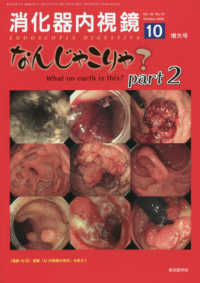内容説明
物質とエネルギーの産業化から、精神の産業化へ―。情報産業社会の到来をいち早く予告し、その無限の可能性を人類文明の巨大な視野のもとに考察した、先見性と独創性に富む名著。
目次
放送人の誕生と成長
情報産業論
精神産業時代への予察
情報産業論への補論
四半世紀のながれのなかで
情報産業論再説
人類の文明史的展望にたって
感覚情報の開発
『放送朝日』は死んだ
実践的情報産業論〔ほか〕
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
saga
35
糸井重里『ほぼ日刊イトイ新聞の本』で良書として紹介されていたので購入。1960年代に書かれた論文「情報産業論」は、まさに21世紀の現代を予見した驚きの内容だ。『情報』の性質を正しく見極めることで、その将来像を言い当てるすごさ! 情報産業は従来の第1~3次産業とは別次元の産業構造なんだ。「情報の考現学」では職種ごとの考察と疑問提起がなされているが、2045年問題と考え合わせた時に、人間とコンピュータをはじめとした情報機器との関係性が逆転してしまうかもしれない未来を想像して少し不安になるな~2015/05/30
chanvesa
26
情報産業時代の明暗を含め、今後の展望は?という問いに対し「それがバラ色の未来につながるかは別問題」とし、『女工哀史』のようなあたらしい生産システムに人間が適合できなかったように「おなじことが二一世紀の初期におこるかもしれない」(148頁)と指摘する。昨今の世界的な排外主義的な投票行動は100年前にも同様なことが起きていた。これが情報が所以であるということではなく、残念ながら賢くならない人間という生物の繰り返し性に起因しているのか。情報産業化がもたらすハレーションの本当の姿はまだ知らないのかもしれない。2025/08/10
高橋 橘苑
23
知の巨人、梅棹忠夫の文章を初めて読む。1963年に於いて将来の情報産業社会の到来を予言している。人類の産業の展開史を、農業の時代、工業の時代、精神産業の時代と捉え、有機体としての人間の諸機能の段階的拡充の歴史として位置づけている。本を読み、音楽を聴き、ニュースを見る。なぜ、それほどに情報を必要とするのだろうか。それは、「感覚器官で受けとめられ、脳内を通過するだけで、感覚器官および脳内神経系をおおいに緊張させ活動させる」からである。現代の我々は、その情報に振り回されている様にさせ思われるが……。2017/02/05
Miyako Hongo
21
頭のいい人間は恐ろしい。トフラーの「第三の波」以前に、同じようなこと考えてた日本人が居たんだよ。□確かに自分ら、洋服を買うのは布地じゃなくてデザインや流行という「情報」を買ってる。食品だって味や形や色やの「情報」を買ってる。食や機能に支払う額より情報に支払う金額の方がはるかに多い。□インターネットで情報が「入れ物」なしで流通可能になったこの現状を、たぶんこの人は予測してたと思う。情報の価格はお布施と同じに決まるとか、情報を出す方が金を払うとか、今日でもはっとする指摘多数。□機会みて深堀したい。2016/12/18
中年サラリーマン
13
なんとはなしに現代の情報化社会を予言している。1960年代なのがすごいね。今は情報は距離の垣根をなくす方向、つまり都市でも田舎でも同質の情報が得られる、に進みSNSとかもその一躍をになっているけれどもそのうち距離ではなく時間軸でも距離を縮める方向にくると思う。著者も触れているが宗教は重要な情報を扱うファンクションだし、僕はこれから復興しそうな気配だと思う。いや、怪しい宗教じゃなくてその考え方なりのはなしだけどね。2013/11/24