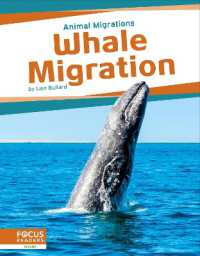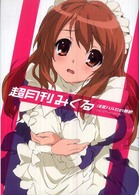内容説明
生と死のきわどいつり橋をわたるように、雪煙を求めて氷壁にたち向っていく尖鋭的アルピニストたち。やがて彼らは、雪煙のなかに消え去った。残された私たちが、鮮烈に生きることをつかの間、思い出すために、彼らアルピニストをいま一度よみがえらせ、その生を解剖する山際ノンフィクションの名作。
目次
第1章 一瞬の生のきらめき
第2章 ザイルのトップは譲れない
第3章 未知の世界に向かって
第4章 山を愛し山に死んだ
第5章 夜明けの美しさのために
第6章 孤高の人生をめざして
第7章 いくつか越える山のために
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
goro@the_booby
49
単独で極限に挑み散った山男たち。今年はアルプス諦めたけど来年は行くぞと強く思った次第です。2020/10/02
ぴよちゃん
3
★★★ 図書館本📘 孤高のアルピニスト。山で読んだら怖いくらいだ2020/08/14
m
1
登山。誰もが気軽に楽しめることは良いと思うし否定はしない。戦後間もなくの時期の登山は、未だ一般的ではなく限られた一部の人だけの世界だった。彼らは、浮世からかけ離れた世界に身をおくことを美徳としていたのだろうか。近寄りがたい雰囲気を発していたとも思う。新田次郎氏の著書は概ね読破したが、モデルとなった登山家の生の生きざまは初めて知った。今の世には存在出来ない(であろう)人々の人生。短いけれど充実していたのだろうか?余談だが、彼らが現在のハイテク装備(道具、行動食、衣類)を持っていたら遭難せずに済んだのか?2024/05/24
中野純二
1
約25年ぶりの再読。ある意味自分の登山趣味と読者趣味、両方の原点かもしれない。 あまり巧みな文章とは思えないけど、山をやる者として熱くなります。2023/09/19
Shoichi Kambe
1
*男にとって“幸福な死”と“不幸な死”があるとすれば、山における死は明らかに前者に属するのではないかと思う。? *五十年代は未踏の高峰に向かって世界のアルピニストたちが激しく闘志を燃やした時代なのだ。エベレスト登頂1953 *未踏の山がなくなったあとは、“条件付きレースをやるしかない。”無酸素、冬、単独、 *一般的に、大学の山岳会は組織的な、秩序だった活動には力を発揮すると言われている。…それに対して民間の山岳会は、一匹狼たちの集まりと言える。2021/10/29



![世界の美しい時間カレンダー 〈2024〉 - BEAUTIFUL TIME OF THE WOR [カレンダー]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/48835/488350624X.jpg)