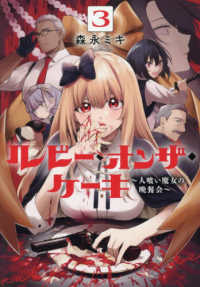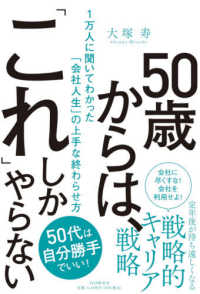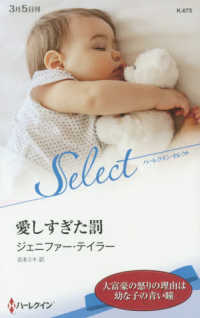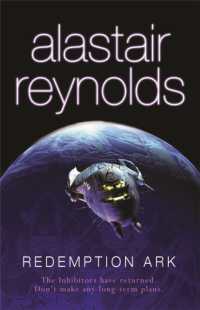出版社内容情報
律令制成立期から南北朝期までの政治史を描き、日本特有の権力構造を鮮やかに解明する。概括となる新章を加え、索引を付した決定版。
内容説明
院政とはすでに譲位した上皇(院)による執政をいう。平安後期に白河・鳥羽・後白河の三上皇が百年余りにわたって専権を振るい、鎌倉初期には後鳥羽上皇が幕府と対峙した。承久の乱で敗れて朝廷の地位は低下したが、院政自体は変質しながらも江戸末期まで存続する。上皇が権力を行使できたのはなぜか。その権力構造はいかなるものだったか。ロングセラーに終章「院政とは何だったのか」を収録し、人名索引を付した決定版。
目次
第1章 摂関期までの上皇
第2章 院政の開始
第3章 院政の構造
第4章 白河院政から鳥羽院政へ
第5章 保元・平治の乱から後白河院政へ
第6章 後白河院政と武家政権
第7章 後鳥羽院政と承久の乱
第8章 鎌倉後期の院政
終章 院政とは何だったのか
著者等紹介
美川圭[ミカワケイ]
1957年(昭和32年)、東京都に生まれる。京都大学文学部卒業。同大学大学院文学研究科に進み、博士(文学)を取得。摂南大学教授などを経て、立命館大学文学部教授。専攻は日本中世史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ホークス
36
2006年刊。理解度7割。道長〜後鳥羽の院政を私なりに解釈 ●藤原摂関家は天皇の外戚として政治を身内化した。道長はその完成者 ●道長は傘下の荘園を増やして財力を、荘園を治める武士を従えて武力も兼備した ●道長後、院の専制化により天皇家は政治力を取り戻す。外戚となる氏族も拡散 ●都の武装勢力(摂関家の武士、院の武士、有力寺社)間の戦いが多発。院も摂関家も武力不足を露呈 ●保元&平治の乱で武士が前面に出る。平氏は摂関家に成り代わる事に半ば成功する ●承久の乱でさらに朝廷の権威は廃れ、王の人事権すら失った。2024/06/08
Toska
20
院政それ自体を俎上に載せるというよりは、摂関黎明期から室町までの長いスパンで政治の流れを概観し、その中で院政が果たした役割を浮き彫りにしていくスタイル。院政を知ることは日本の中世史を知ることでもある。白河〜後鳥羽の院政最盛期は上皇たちの強烈な個性に任せたプリミティヴな専制にすぎず、寧ろ承久の乱以降に制度的な洗練が見られる等、新たな発見が多かった。「あとがき」と「増補版あとがき」が妙に文学的。2024/11/07
白隠禅師ファン
16
院政の構造、変遷(白河-後鳥羽までが中心)がよくわかりましたね。院政に関しての知識はふわっとしていたのですが、わかりやすかったので面白く読めました。あと保元・平治の乱は自分が思っていたより、人間関係が複雑に絡み合っているように感じましたね。僕だけ?2024/06/21
maekoo
13
源氏物語の享受史を調べていると白河~後鳥羽時代の院政を知る必要が出て来ます。 特に白河法皇の源氏物語絵巻創作プロジェクトや後鳥羽院の定家との和歌を通じたプロジェクト等は、どんな財政基盤が有りそれを成しうる権力をどう掴んだかを学ぶと色々深めれます! この本はその院政について、上皇の誕生から摂関政治との絡みや南北朝時代以後の室町時代の義満の院政取り込みによる院政の終わりまで、平安時代の後三条院から後鳥羽院までを中心に歴史的事件と政治状況と共に年代を追って詳しく解説して下さっています。 膨大な参考文献はとても◎2024/06/22
スターライト
13
「院政」は天皇が子どもに譲位して権勢をふるい、その代表格は承久の乱の後鳥羽上皇、という程度の知識しか持っていなかった。その「院政」の開始から終焉までを丹念に追った書。上皇の始まりは確実な皇位継承権のためであり、その後政治的権力の面が拡大していったようだ。そこには身内内での争いから、やがて国家の命運を左右する過程が現れる。特に武士が力を持つにつれ、天皇の権威の浮沈が激しくなり、幕府の意向抜きには人事もままならない事態になっていく。江戸時代後期まで院政が存在していたのには驚き。2021/06/10
-
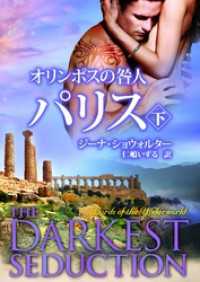
- 電子書籍
- オリンポスの咎人 パリス 下 ハーレク…