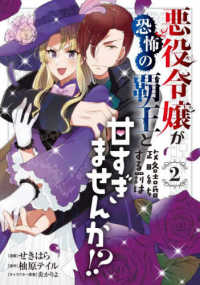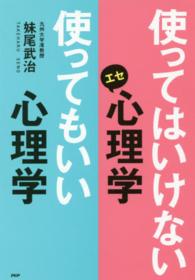出版社内容情報
『暗黒日記』で知られる清沢の外交評論は、国際関係を考える上でいまなお有効だ。
内容説明
『暗黒日記』の著者として知られる清沢洌は、戦前期における最も優れた自由主義的言論人であり、その外交評論は今日の国際関係を考える上で、なお価値を失っていない。石橋湛山、馬場恒吾ら同時代人のなかでアメリカに対する認識が例外的に鋭くあり得たのはなぜか。一人のアメリカ移民が邦字新聞記者となり、活躍の舞台を日本に移してから、孤独な言論活動の後に死すまでの軌跡を近代日本の動きと重ねて描く唯一の評伝。
目次
序章 青年時代
第1章 新聞記者時代―国際協調と政党政治
第2章 評論家としての独立―国際協調の崩壊
第3章 自由主義者の孤独―日本外交の混迷
第4章 評論から研究へ―日中戦争と日米戦争
補章 若き日の清沢洌―サンフランシスコ邦字紙『新世界』より
著者等紹介
北岡伸一[キタオカシンイチ]
1948年(昭和23年)、奈良県に生まれる。1971年(昭和46年)、東京大学法学部卒業、76年、同大学大学院博士課程修了。法学博士。立教大学法学部講師、助教授、教授を経て、97年より東京大学法学部教授。専攻、日本政治外交史。2004年4月より、国連代表部次席大使を務める。著書に『日米関係のリアリズム』(中公叢書、1991年。読売論壇賞受賞)、『20世紀の日本1 自民党―政権党の38年』(読売新聞社、吉野作造賞受賞、1995年)など
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ほうすう
12
昭和期において評論家として活躍された清沢洌の業績をたどりながら彼を通して戦前戦中の日米関係を描く。名前だけ聞いていた方だが所々には欠点なども垣間見えたり、葛藤するさまがにじみ出たり思っていたより人間味があるように感じられた。完全な在野というのか分からないが政府から距離を置いた人物から見る戦争への外交過程はなんとももの悲しさのようなものがある。2024/03/16
masabi
10
【概要】評論家清沢洌の生涯と思想を解説する。【感想】在米邦人社会でも本国でも一定の距離を取った結果、怜悧な分析と他者に阿らない文章で戦中まで自由主義を貫く評論家として活躍する。アメリカ的気風と皇室主義者を兼ね備えた異邦人でもあった。自由主義を貫けたのは要因の一つは盤石な経済基盤にある。執筆と講演に精力的で、日本社会を支える国民の意識改革という目的に加えてフリーランスの不安定さを補う意味があった。戦中に評論の公開が禁じられた時も農業と併せて生活できた。2022/04/07
バルジ
6
再読。最後まで日米の協調と日本への愛国心を抱いた一人の評論家を論ずる名著。戦争や国家との向き合い方を考える上でも清沢洌のその生涯は極めて参考になる。印象的な点は既に自由主義的知識人として名を馳せていた1930年代、政府の委嘱で欧米での対外宣伝活動に従事した際の清沢の態度である。平生は日本の武力を用いた対外進出に異を唱えていた清沢であるが、この時ばかりは日本の正当性を主張して止まず自嘲する程の「愛国者」となっていた。いかに「自由主義者」であっても国家を背負う時、どのような態度となるか一つの例になろう。2022/04/30
のん
4
以前、Twitterで誰かが清沢洌『暗黒日記』をおすすめしており(『暗黒日記』は未読)、それ以来「清沢洌」という人物が気になっていた。戦前の自由主義者で日米関係が専門の評論家。1906年に渡米し、在米邦人向けの新聞の記者となる。その記事が在米邦人の間で話題となり、のちの言論活動の足がかりをつくる。2025/11/15
編集兼発行人
4
我国において戦前に活躍した外交評論家に関する評伝。高等教育とは無縁の苦学と排日が盛んな米国での移民体験とを礎にしながら言葉を駆使して頭角を現わし局地的かつ情緒的な観点が多勢を占める時代において大局的かつ政治経済的な見地でもって論旨を展開し孤軍奮闘する主人公の姿について時系列で克明に描写。邦人ばかりの世間にて共有される言論はロジックではなくセンチメントに基づくという哀愁の現実を目前に尚も論理的な主張を止めない気骨の背景として精力的な執筆が齎す収入を活用した巧みな財テクが控えるという合理的な処世術に頗る合点。2014/10/26