内容説明
体制が崩壊の危機に直面したときこそ政治家の力量が試される。それぞれの思惑を秘めて画策する朝廷と雄藩と幕閣との複雑微妙な幕末の政治動向の渦中で、最後の将軍はどれほど時代の展望をもっていたのか。英名の君主ともいわれ、凡庸な野心家にすぎないとも評される多面的な人物像の真実を明らかにすると同時に、武家政治の終焉に立ち合うことになった徳川慶喜という悲運の将軍の心情と行動様式を通して、国家とはなにかを考える。
目次
1 水戸に育つ
2 将軍不在
3 慶喜後見職
4 禁裏守衛総督
5 最後の将軍
6 壮年閑居
7 昔夢会の虚実
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
lila*
3
【図書館】幕末期が舞台の小説を続けて読んでいて、一番気になったのが徳川慶喜。ちょっと調べると大正まで生きていて、晩年には当時のことについて語っていたりとますます気になって。本書の中でも当時を振り返っての言葉が時折出てきていた。巻末の参考文献の紹介には著者のコメントも添えられていて、これらもまた気になる。2016/06/26
本命@ふまにたす
2
徳川慶喜の人生を幕末史の中で語る。あくまでも慶喜にフォーカスしつつも、幕末史に関する展望も得られるものとなっている。また、巻末に徳川慶喜に関する写真が収められており、その点も興味深い。2022/04/28
cybertiger
2
幕末の主導権争いが克明に記されており、非常に充実した内容だった。慶応三年10月14日の大政奉還に伴う朝廷の動きは12月9日の王政復古のクーデターで断ち切られる。薩長は、辞官納地によって慶喜を挑発し鳥羽伏見の戦いに追い込む。目指すところは慶喜も薩長も列侯会議だったようだ。当初は、どちらが主導権を握るか、という争いだった。大政奉還を出した後、朝廷の動きを見定めて、諸外国の公使を大阪城に集め我が国の正当政府は徳川幕府だと宣言する。慶喜の一筋縄では行かない面が活写されている。2021/06/01
A.KI.
2
江戸幕府最後の将軍、すなわち日本の歴史上最後の将軍である徳川慶喜の生涯をひも解きながら、同時に幕末・維新史も学べる。司馬遼太郎の小説などで聡明な人物像のイメージが強い慶喜。それはたしかに間違いないのだろうが、本書を読むと、それゆえに常に微妙な立場に置かれ、それゆえにさまざまな局面で難しい判断を迫られたという印象。どんな立場にいるかというのも大事なんだなあとしみじみ。30代半ばで隠居、その後の余生のが長いわけだが、時代の大転換期をなんとか軟着陸させた苦労を思えば、余生を過ごせてよかったなあと思う。2021/03/07
DualBlueMoon
2
45年間ものんびり生活できたのがうらやましい。それだけ若い頃に頑張ったということなのか。2018/01/22
-
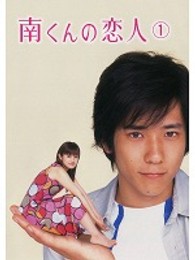
- DVD
- 南くんの恋人 第1巻







