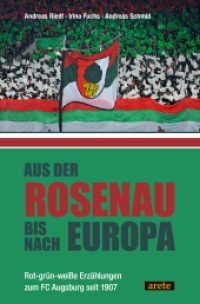内容説明
人間は虚無から創造することはできない。未来への情熱がいかに烈しくても、現在に生きている過去をふまえずに、未来へ出発することはできない。私たちは、明治維新から一九四五年までの日本人の思想的苦闘の跡をどれだけ知っているであろうか。日本の未来を真剣に構築しようとするとき、私たちは近代の思想遺産―少なくともこれらの五〇の名著は活用せねばならぬはずである。私たちは近代国民としての自信をもって、過去に不可避的であった錯誤の償いにあたるべき時期にきている。
目次
福沢諭吉『学問のすゝめ』
田口卯吉『日本開化小史』
中江兆民『三酔人経綸問答』
北村透谷『徳川氏時代の平民的理想』
山路愛山『明治文学史』
内村鑑三『余はいかにしてキリスト信徒となりしか』
志賀重昂『日本風景論』
陸奥宗光『蹇蹇録』
竹越与三郎『二千五百年史』
幸徳秋水『廿世紀之怪物帝国主義』〔ほか〕
著者等紹介
桑原武夫[クワバラタケオ]
1904年福井県に生まれる。1928年京都帝国大学文学部卒業。京都大学人文科学研究所教授、同所長を経て、1968年に定年退官、名誉教授となる。1987年文化勲章を受章。専攻は西洋文化史。1988年逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
35
福沢諭吉では、国民の力と政府の力と互に相平均させることを期待している(10頁)。田口卯吉では、生産の発達が文化の発達を促すとした(13頁)。中江兆民『三酔人経綸問答』で、奇説の南海先生、言語明晰な洋学進士、和服の壮士風な豪傑君が登場(19頁)。昔の国Ⅰキャリア採用教養試験過去問で見た記憶がある。アルフレッド・マーシャルは経済学は生物学になるとしていたようだが、北一輝も社会主義の基礎は生物学としていた(92頁)。彼はマーシャルに影響されてのことであろうか? 河上肇も結果的には国家の力を容認(136頁)。2016/02/20
Tomoichi
25
1962年に編された本で、明治維新から敗戦までの日本人の思想的苦闘の跡を辿れる近代思想の書を選んでいる。しかしながら唯物論や共産主義全盛期のものなので21世紀の今、もうコミュニストの本を「名著」と呼ぶ人は誰もいない。現代のコミュニストだって羽仁五郎を読みますか?ブルジョアコミュニストの羽仁五郎ですよ。当時も今もプロレタリアートは誰も読まない。だってインテリゲンチャの言葉遊び・エリート主義に誰がついていく。本書の価値は、当時何が名著とされていたかという時代雰囲気だけである。2024/06/22
双海(ふたみ)
24
「健康な民主主義的啓蒙史観」という言葉があって、私は飲んでいたお茶を吹き出しそうになりました。これほど不健康なことはそうはない。啓蒙だなんてイヤらしい。2015/07/20
にゃん吉
8
明治維新から終戦前の日本の名著を紹介。名著の選択、名著たる所以の解説に、1960年代の雰囲気を感じるところもありますが、それはそれで貴重ともいえ、また、解説担当者の顔ぶれは豪華というほかなく、中公新書の一冊目に相応しい堅実さ、重厚さのある一冊ではないかと思われました。個人的には、名著の著者の顔写真が載っているのがよかった。名前を知っていたり、さらには、著書を読んだことがあったりしても、意外と著者の顔写真を見たことがないのに気づきました。丸山真男氏の写真など、意外な印象。2020/02/03
Nobu A
7
1962年初版の改訂版を読了。明治維新から現代までの優れた本を50冊紹介。気軽に読むつもりが、意外に密度が濃く難解。なかなか頁が進まず、図書館の返却日を過ぎながらも、なんとか読了。久鬼周造の「いきの構造」(以前に一度読んだことがあるような気がするので、再読かも)、中井正一の「美と集団の倫理」、山田盛太郎の「日本資本主義分析」、波多野精一の「時と永遠」、今西錦司の「生物の世界」、小倉金之助の「日本の数学」と鈴木大拙の「日本的霊性」を読まずして死ねないなと思った。偉大な先人達が残した名著を心して読まなければ。2015/11/12
-

- 電子書籍
- .hack//G.U. Begins【…