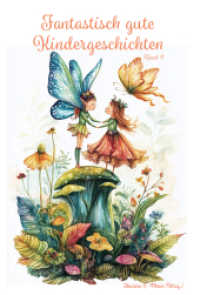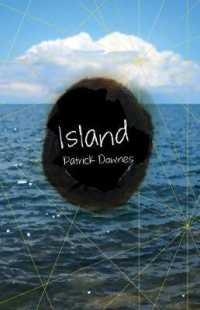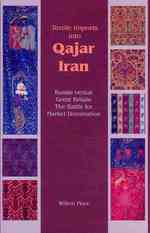出版社内容情報
兜{と}巾{きん}、白衣の結{ゆい}袈{げ}裟{さ}、錫{しやく}杖{じよう}をつき、笈を背に法{ほ}螺{ら}貝{がい}をふく、いまでも出羽三山、大峰山中に出没する山伏・・。年二回先達に従って入{にゆう}峰{ぶ}し、水断、穀断、懺悔、相撲などの苛酷な修行で体得した験力により、加持祈祷の呪法を行なう彼らのなかには、中世の最盛期を過ぎると修行を忘れ、まじない師に堕するものもあらわれた。本書は、民間信仰に仏教が結びついて完成された修験道の真髄を、山伏の奇怪な行事、生態のなかにさぐる。
内容説明
兜巾、白衣の結袈裟、錫杖をつき、笈を背に法螺貝をふく、いまでも出羽三山、大峰山中に出没する山伏―。年二回先達に従って入峰し、水断、穀断、懺悔、相撲などの苛酷な修行で体得した験力により、加持祈祷の呪法を行なう彼らのなかには、中世の最盛期を過ぎると修行を忘れ、まじない師に堕するものもあらわれた。本書は、民間信仰に仏教が結びついて完成された修験道の真髄を、山伏の奇怪な行事、生態のなかにさぐる。
目次
1 山伏の印象
2 山伏の起り
3 中世山伏の活動
4 峰入り修行
5 山伏の組織化
6 定着山伏の実態
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
nemunomori
8
古代の山岳信仰に端を発する修験道は、密教や陰陽道などと結びつきながら日本人の日常生活に深く根付いていきます。本書はその歴史を紐解きつつ、山伏という怪しげな存在を分かり易く解説しています。人里離れた霊山に登って凄まじく過酷な修行をすれば、いつか呪法を行う験力が得られるという信仰はなんとなく腑に落ちるものでした。日本人が山に抱いてきた神聖なイメージが、未だに自分の中にも息づいていると思うと不思議な気がします。2016/01/26
maqiso
6
山岳信仰に密教が結びついて山々で激しい修行が行われるようになった。平安貴族は熊野詣でを好んだが、不安定な中世になると修験道はさらに広まる。山を移動して修行する山伏も数が増えると組織化され、天台系と真言系の2派に分かれ、峰入りの回数で上下が決まった。教義は実際の山伏や修行に合わせて作られた。修行による験や呪術が庶民から信仰されたが、地方に定着して檀家を持ち、戦国期にかけて政治化していくものも多い。2022/10/26
とこ
3
山伏のイメージは漠然とつかめたが、少しわたしには難解な本でした。あれ、山伏って時の権力とは離れた場所にいるものではなかったの?もっと色々読んでみよう。2012/12/11
マープル
3
以前テレビで山伏のドキュメントを見たとき、めちゃめちゃ体育会系ののりでドン引きしたのだが、昔からそうだったようです(笑)。なんとあの西行が泣かされたくらいだそうで。シゴキが精神性につながるという日本のスポーツ・軍隊に見られる民族性のもとはこのへんにあるのかもしれない。病根は深いな・・・2011/11/22
なをみん
2
明治5年9月以来、いなくなったことになる山伏の歴史的な話。個人的にはドカベンの弁慶高校のイメージでずっとなんとなく気にはなっていたけど知る機会がなかった。宗教的であり世俗的あり神仏混淆的という存在であったことは、なんとなくわかりました。そういう存在を必要としていた日本の歴史というかなんというか、ちょっと昔の忘れそうな日本人のリアルな宗教的感覚のようなものをもうちょっと知りたいのだけれど。2024/12/13
-
- 洋書
- Island