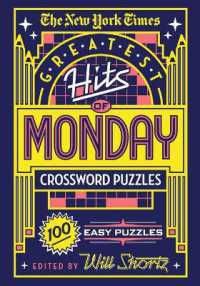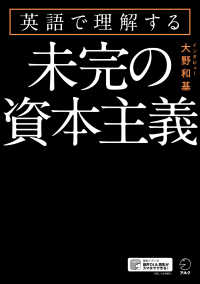内容説明
観念論的法思想を超えた法社会学の先駆。著者自身が自負する代表作。三権分立を論じ合衆国憲法やフランス革命に影響を与えた一書。
著者等紹介
モンテスキュー[モンテスキュー] [de Secondat,Baron de La Br`ede et de Montesquieu,Charles‐Louis]
1689‐1755。フランスの啓蒙思想家。ボルドー近郊で生まれ、長じて法律家として高等法院に勤めるが、絶対王政末期のフランスにおける不条理な政治や思想を軽妙に風刺した『ペルシア人の手紙』で注目された。歴史的世界として古代ローマに関心を持ち、匿名で『ローマ盛衰原因論』を執筆した後、45歳ころからの起筆にとりかかる。出版は59歳のとき。啓蒙主義の思想的勝利を画した書物と考えられている
井上堯裕[イノウエタカヒロ]
1936年名古屋市生まれ。東京大学大学院卒業。聖心女子大学教授を経て名誉教授。西洋史、フランス社会史専攻。2002年逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かわうそ
41
本来、政体の原理と教育の原理、法の原理は一致しているべきです。本書では関係すると記載されていますが、要は政体の原理が染み渡っているべきであるということです。例えば、共和制であれば、政治的徳性(祖国への愛と平等への愛)が教育の根底にも浸透しているべきですし、専制であれば恐怖という情念が支配的です。また、君主制は名誉への愛で構成されます。また、モンテスキューの議論において注目すべき点は政治体を君主制、専制、共和制 (民主制、貴族制)に分けている点です。民主制と貴族制は権力がある一定の主権者が握っている点2022/11/11
1.3manen
41
パリのサロン:コーヒーハウスでの対話、新聞・雑誌の朗読はハーバーマスの市民的公共圏の苗床(5頁)。民主制の原理は、平等精神を失うときや、極度の平等の精神を持ち、各人が自分を支配するために選んだ者と平等たろうと欲するときにも腐敗する(100頁)。社会は平等を失わしめる。人間は法によってのみふたたび平等となる(103頁)。自由とは、望むべきことをなしえ、望むべきでないことをなすべくけっして強制されないこと(127頁)。2016/05/16
加納恭史
18
昨日はユンニの湯に出かけ、車で暑さをしのぐ。由仁町の高台にある温泉は空気も清々しい。読書の疲れも取れて、今日は「法の精神」の手引きとなるこの本を見つけて読む。「法の精神」につき、法の風土と歴史の観点から善き解説だな。やや啓蒙思想にも慣れて、ルソーより丁寧な法律論議となっているな。モンテスキュー(1689~1755)はヴォルテール(1694~1778)とだいたい同世代だな。フランスの絶対王政のルイ十四世(1638~1715)の時代だな。彼は旧貴族の長男として生まれた。幼少の頃母親の死で男爵領を相続した。2023/08/02
ともブン
9
人間の本来の姿と理想の姿(哲学・宗教)や生産活動、税(経済)について論じた上でようやく法律のあるべき姿へ流れていくのは必然なのだろう。本書もしかり。 「貢租の重みはまず労働の荷重を生み、衰弱を、そして怠惰の精神を生み出す」「国家の理想的な必要のために人民からその現実に必要とするものまでもを取り上げてはならない」(職人の数を減らすような機械は有害」などは現代日本に通じる気がする。あと所々に日本が例に挙げられているがキリシタン弾圧は100年後のフランスでも語り継がれるほどにショッキングだったんだと感慨深い。2024/04/21
あんどう れおん
4
丁寧な抄訳。収録されなかった部分についても、見出しの邦訳を目次で確認することができます。法律だけではなく、幅広い領域を論じている点が特徴の一つだろうと思います。引用は差し控えますが、初版の翌々年(1750)以降の版では削られたという、日本語だと(句読点を除いて)87文字に及ぶ副題を構成する「習俗」やら「商業」なる語句だけでも、一筋縄ではいかない感じが伝わってくるようです。いつの日か有名な古典の全編に取り組む意欲をお持ちの方には、よい導入の一冊となってくれるかもしれません。2022/11/28
-
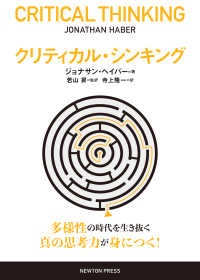
- 和書
- クリティカル・シンキング