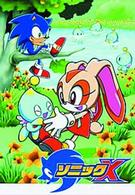内容説明
十九世紀のヨーロッパに秩序と安定、四十年の平和をもたらせた「勢力均衡」の知恵とは何か―。
目次
1(近代ヨーロッパの勢力均衡)
2(ウィーン会議と「ヨーロッパ」;会議はなぜ踊りつづけたか)
著者等紹介
高坂正堯[コウサカマサタカ]
1934~96。国際政治学者。哲学者・高坂正顕の次男として生まれる。京都大学法学部で国際法学者・田岡良一に師事し、卒業後ハーヴァード大学留学。1963年『中央公論』に「現実主義者の平和論」を発表して論壇に登場する。冷戦時代から共産主義国家には批判的で、現実に即した保守政治評価や国際政治観を表明した。専門は国際政治学、ヨーロッパ外交史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
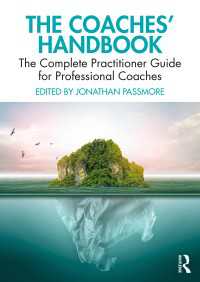
- 洋書電子書籍
-
コーチング実務ハンドブック
Th…
-

- 和書
- 恋愛論 〈下〉 岩波文庫