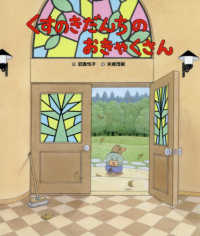出版社内容情報
「日本経済は美しい白鳥になる」――池田内閣の国民所得倍増計画、日本の高度経済成長のメカニズムを理論づけた書
目次
1 成長政策の基本問題(成長政策の基本問題;経済成長の可能性と条件;成長政策の基礎理論)
2 経済成長に関する若干の諸問題(日本経済と成長政策;経済成長と自由化について;経済成長と金融政策のあり方;経済成長の金融的条件;経済成長と景気循環)
3 当面の情勢と経済成長(米国のドル防衛と日本の経済;当面の経済情勢とこれに対処する基本的態度;9%の成長に不安なし;日本経済の現段階と経済成長;日本経済の歴史的位置づけのために)
著者等紹介
下村治[シモムラオサム]
戦後日本経済に最も大きな影響を与えたエコノミスト。1910年(明治43年)佐賀県生まれ。1934年(昭和9年)東京帝国大学経済学部卒業後、大蔵省に入り、59年退官までの間に経済安定本部物価政策課長、日銀政策委員などを歴任、独創的な理論経済学者として知られた。退官後は国民金融公庫理事、日本開発銀行理事などを務めた。昭和30年代後半の池田内閣の国民所得倍増計画立案に中心的役割を果たし、日本の高度経済成長のメカニズムを体系づけた。『経済変動の乗数分析』により経済学博士。1989年(平成元年)逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Kaz
20
ところどころ理解の範囲を超える内容となっていたが、著者が単なる頭でっかちの役人ではなく、胆力においても卓越した経済官僚であることは伝わってきた。1950年頃の経済情勢をベースに論述されているが、基本となる考え方は今でも生きていると思える。日頃感じていることだが、以下のくだりを読み、経済や技術が時代の底を揺り動かし、社会や政治が追従するということを再確認した。2015/03/12
isao_key
3
下村治の名前を知ったのは、沢木耕太郎『危機の宰相』を読んでからだった。そこには池田内閣時代の所得倍増計画を実現させた人物として田村敏雄とともに下村治の名前があった。その著者の書いた昭和37年の同書を底本として2009年に新たに中公クラッシックスとして出版したのがこの本である。内容的には統計やグラフが多く、経済用語、経済の基本的な考え方を理解していないと読み進めるのはたやすい作業ではない。読んでいて楽しいという本ではないが、昭和30~40年代のダイナミックな日本経済の成長過程の動きを知ることができる。2012/05/09
ぽん教授(非実在系)
2
下村は低賃金カルテルによる経営を厳しく戒めている。なぜならば、高賃金化→設備投資→生産力上昇→経済成長→高賃金化…という流れこそ経済成長の根幹だからである。単なる経済成長自体が目的ではなく、国家国民の発展を意図している下村はナショナリズム的である。経済成長の理論の下敷きはケインズの高弟ロイ・ハロッド(ハロッド・ドーマーの定理)であることが窺える。2020/08/04
よし
0
設備投資が経済成長のキモ。旺盛な需要と良質な労働力が高度経済成長を支えたのですね。小難しい数式が並んでるのかと思いきや意外と現実的な面からの考察が多く、とても勉強になった。とはいえ、まだまだ理解できない部分が多く、もう少し理解を深めて再読したい。2013/06/09
gonbee
0
日本経済全般について語られているが、特に響いたのは農業に関する部分。日本全体が成長する中で、農業も生産性が向上し、競争力を持ち、というように語られているが、未だに実現しないまま高齢化によって日本の農業は自滅して終わりかねない。30年代の著作の抜粋だが、晩年の物も読んでみたい。そして亡くなった直後に失われた20年、存命ならどう見たのだろうかと興味がわいた。2013/01/05