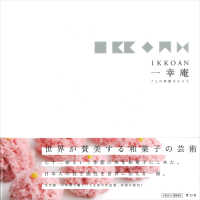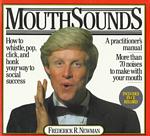出版社内容情報
田園調布や六本木ヒルズ、山谷地区やシャッター通り、ホームレスが住む公園まで。東京23区内をほんの数キロ歩くだけで、その格差の宇宙が体感できてしまう。東京は、世界的にみて、もっとも豊かな人々と、もっとも貧しい人々が住む「階級都市」だ。そんな23区の姿を、格差に関するさまざまなデータをもとに詳細に分析。その実態を明らかにするとともに、「階級都市」が潜む危うさを、どう克服すればいいのかについても考えていく。
内容説明
田園調布や六本木ヒルズから、山谷地区やシャッター通り、ホームレスが住む公園まで―。東京23区には、文化やテイストの違いだけではすまされない、格差と階級が存在する。100点以上もの豊富な図表と写真で、この多様で個性的な地域の実態を明らかにし、そこに潜む危うさをいかに克服するかを探る。
目次
序章 東京23区―格差と階級の巨大都市
第1章 階級都市・東京の空間構造―「都心」「下町」「山の手」
第2章 「下町」と「山の手」の形成と変容―階級闘争の場としての都市空間
第3章 東京23区のさまざまな姿―社会地図が示すもの
第4章 東京23区のしくみ
終章 交雑する都市へ―「下町」「山の手」の二項対立を乗り越える
著者等紹介
橋本健二[ハシモトケンジ]
1959年石川県生まれ。早稲田大学人間科学学術院教授(社会学)。東京大学教育学部卒業、同大学大学院博士課程修了(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





乱読太郎の積んでる本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ykmmr (^_^)
130
在・東京。そろそろ10年。正直、内容的に予想通りではあった。23区。それぞれの区が、特徴があり、味があり、在り方がある。ただ、問題はその区ごとに落差があり、富裕・貧困層が乱立してしまっている事だ。著者は『都営住宅』・『古びた家』でそれを表現しているが、実際はそれだけではないとも思う…。さらに、その落差を埋めるのは困難だが、その地域の姿を知ることで方法はありそうだが…。しかし、今のご時世じゃ、これからどうなるのか?10年クラスで、今の状態じゃやって行けないわ。都内から出るのも、鮮明な選択なのかも。2022/01/21
キク
64
僕は色々問題はあるけど、出身や人種への偏見は全然ない。ブルハの「生まれたところや皮膚や目の色で、僕の何がわかるというのだろう」という歌声を聞いて育ったから、ではない。単純に処理能力が低いので、物事の判断基準に入ってこない事柄への関心が皆無だからだ。そんなことにこだわって生きていく余裕はない、ということだ。でも本書を読むと、課税対象所得の平均が1番高い港区(583万円/人年)と足立区(156万円/人年)では約4倍違う。そこには間違いなく格差と階級がある。でも、だからなんだよと思う。、、、処理能力が低いので。2023/09/14
おかむら
36
港区と足立区では平均世帯年収に4倍もの差がついている。まあなんとなくわかってたけど、23区の格差を豊富なデータで解析。自分だったらどこに住むかを妄想しながら読みました。渋谷区幡ヶ谷あたりがいいなあ。義母が港区の都営アパートに住んでるんですが、最寄りのスーパーがまいばすけっと(元コンビニで狭い)と東京ミッドタウンのプレッセプレミアム(東急ストアの高級なやつ)の2ヶ所しかなくて超不便。年金暮らしの高齢者には向かない街だわ。2021/11/14
よしのひ
20
「東京23区」というだけで何だかすごいな~という感想を今まで持っていましたが、今作を読んでその23区内でも多様に特徴があるのだということが1つの発見でした。単に1つの項目だけで比べるのではなく、様々な項目を駆使しその結果から読み取れる傾向が記されていたので、読み手にも十分に説得力ある調査結果であったのではないでしょうか。また終章では新型コロナウィルスからの最新データからの考察があり、それに加えて教育に関することも記載があったので、「今」を勉強している感覚にもなりました。東京が「交雑都市」へと進んでほしい。2021/09/20
ゆう
12
時間つぶしのつもりで手に取った本だったが、思いのほか読み応えがあった。著者は40年近くにわたって、格差と階級について研究している。東京という都市は巨大かつ複雑で、その実態を一言で説明するのは難しいが、本書では複数の視点から作成した「社会地図」を見比べる手法によって、「階級都市」としての東京の姿を立体的に描き出すことに成功している。2025/01/21
-
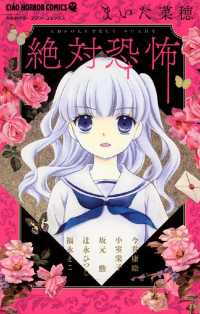
- 電子書籍
- 絶対恐怖 ちゃおコミックス