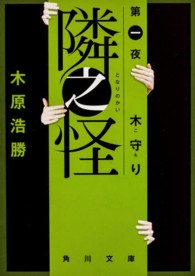内容説明
明治14年、大学を卒業したばかりの若き学徒たちが、高い理想に燃えて設立したわが国最初の私立理学学校。その波瀾万丈の歴史と理科教育者、理科学生の群像を描いた名作。
目次
黎明期の物理学徒
物理学校開校
山川健次郎
名物教師の群像
設立一〇年
日清戦争時代の物理学校
中央気象台
鮫島晋
大正時代の物理学校
震災をへて昭和へ
最後の“生き証人”
戦時下の物理学校
著者等紹介
馬場錬成[ババレンセイ]
東京理科大学知的財産専門職大学院教授。1940年東京都生まれ。東京理科大学理学部卒、65年読売新聞社入社。社会部、科学部、解説部記者を経て論説委員。2000年退社し、現在、科学ジャーナリスト。著作活動のほか「特定非営利活動法人21世紀構想研究会」理事長、科学技術政策研究所客員研究官、早稲田大学、東京理科大学講師として活躍したのち現職。内閣府重点分野推進戦略専門調査会委員、経済産業省、文部科学省の各種委員も務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ちくわん
6
明治維新に始まる日本の西洋「理学」教育に奔走した集団(最終的には東京理科大学)の話。最初が江戸最終末期から明治、大正、昭和、第二次大戦後までを駆け抜ける。学問的な記述はなく、人及び組織、建物を扱う。「うわ~ぁ、こうして私立大学はできたんだ」って感じ。脇役になるが「山川健次郎」氏の人生が壮絶だ。2018/01/03
オランジーナ@
1
物理学校は東京理科大学の前身の学校である。本書は物理学校を中心に日本の近代史において、国家の縁の下の力持ち的存在である理学の普及に情熱を捧げてきた男たちの人生の記録が読みやすく描かれている。朝ドラで放送したら理学を志す若者が増えるのではないかと思います。2015/08/30
さらちゃん
0
明治の人は、自己犠牲なのか、自己結実の手段なのか、歴史を創ることを意図していたのか、今われわれのすべきことをあらためて、考えさせられる2014/02/16
MAT-TUN
0
明治時代の若き学徒の情熱が、物理学校(現在の東京理科大学)を生んだ。その過程が、さまざまな魅力的な登場人物とともに力強く描かれている。本書を読むと改めて物理学に対して熱い気持ちが湧いてくる。2011/11/13
あ
0
近代史のなかの理科学生という副題がすごくいいなと思ったのだけど中は全然でした。2020/11/20


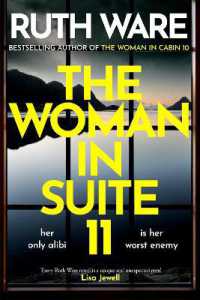
![[標準]初級からのヴァイオリン二重奏 - ファースト・ポジションで楽しむアンサンブル (第2版)](../images/goods/ar2/web/imgdata2/41132/4113221111.jpg)