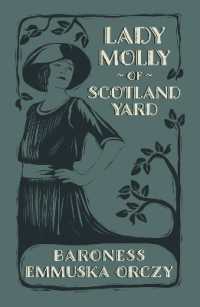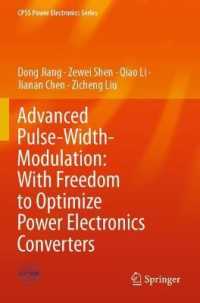内容説明
情報過多社会で身につけたいリテラシーの要諦とは。真偽を見抜き、必要性を判断するために、手引きとなる一冊。一つ一つの情報の真偽や必要性を判断し、活用していく「情報力」を培うためのヒントを数多く収録。
目次
第1章 情報平準化のおそろしさ(一日に新聞六〇〇〇ページ分;増大した情報の中身 ほか)
第2章 「みんな」とは誰のことか?(編集の意義;ポータルサイトのニュース ほか)
第3章 情報のウラを「読む」(情報を見極める;情報の信ぴょう性 ほか)
第4章 情報を「選ぶ」訓練をする(“コピー&ペースト”はなぜいけない?;「正解」はどこにあるのか ほか)
第5章 インターネット時代の情報リテラシー(日本の情報教育の現状;日本のデジタル読解力は世界第四位 ほか)
著者等紹介
上野佳恵[ウエノヨシエ]
津田塾大学国際関係学科卒業後、株式会社日本能率協会総合研究所マーケティング・データ・バンクにて会員企業向けの情報提供サービスに携わる。のち、マッキンゼー・アンド・カンパニーインクジャパンに転じ、国内外コンサルタント・クライアントに対するリサーチ、コンサルタントに対するリサーチトレーニングなどを担当。2001年リサーチ関連サービス、コンサルティングを行う有限会社インフォナビを設立。各種のリサーチ・コンサルティングプロジェクトに携わると共に、新入社員から戦略スタッフまでの情報力スキルアップ研修等を実施(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Tadashi_N
壱萬参仟縁
キリル
たいそ
ちいくま