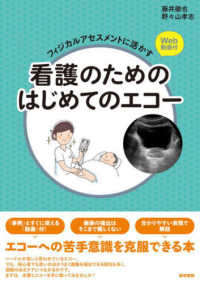出版社内容情報
大日本帝国陸軍の変化を、デモクラシーとの関わりに着目して論じる試み。軍と社会が影響を与え合った経緯を描き出し、近現代日本の一面を照らす。草創期の栄光と挫折、大正デモクラシーと軍縮、そして急速な政治化の果てに待っていたものは――。
【目次】
内容説明
陰湿、粗暴、狂信的…と語られてきた大日本帝国陸軍。しかし実際には、建軍当初から、国際的視野を持つ開明的な将校などは多く存在していた。一九四五年の解体までの七十余年で、何が変化したのか―。本書は、日露戦争勝利の栄光、大正デモクラシーと軍縮、激しい派閥抗争、急速な政治化の果ての破滅まで、軍と社会が影響を与え合った軌跡を描く。陸軍という組織を通し、日本の政軍関係を照らす、もう一つの近現代史。
目次
第1章 栄光からの転落
第2章 第一次世界大戦の衝撃
第3章 ポスト大戦型陸軍への挑戦
第4章 「大正陸軍」の隘路
第5章 「昭和陸軍」への変貌
第6章 陸軍派閥抗争
第7章 政治干渉の時代
第8章 日中戦争から対米開戦へ
終章 歴史と誤り
著者等紹介
〓杉洋平[タカスギヨウヘイ]
1979年生まれ。中学校卒業後、海上自衛隊生徒(41期)を経て國學院大學文学部史学科卒業、同大学院法学研究科博士課程後期満期退学。宮内庁書陵部編修課(非常勤)を経て同上大学院再入学、同修了。博士(法学)。日本銀行金融研究所(個別事務委嘱)などを経て、帝京大学文学部史学科准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
kk
Hiroshi
まんぼう
Tomozuki Kibe