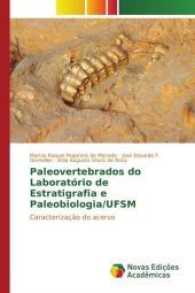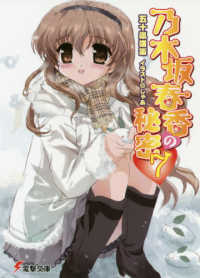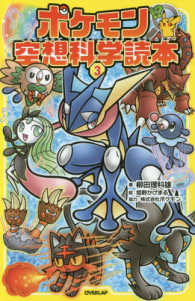出版社内容情報
デジタル化やグローバル化などの社会変化を背景に、世界各国が教育改革を加速させている。
本書はOECDやユネスコなどの国際機関、各国での議論を踏まえ、これからの教育の方向性を考察する。
世界が求める能力や主体性、ウェルビーイングとは何か。
各国が直面するオーバーロードや教師不足の対応策は。
そして、日本の教育に欠けているものは何か。
一人一人の子供が尊重された、あるべき教育、学校の未来を探る。
内容説明
デジタル化やグローバル化などの社会変化を背景に、世界各国が教育改革を加速させている。本書は国連やOECD、ユネスコなどの国際機関、各国での議論を踏まえ、これからの教育を考察する。新たな時代に求められる能力や主体性、ウェルビーイングとは何か。各国が直面する教師不足や過重なカリキュラムへの対応策は。そして、日本に欠けている点とは。一人ひとりの子供をが尊重された、あるべき教育、学校の未来を探る。
目次
序章 変わる世界の教育
第一章 教育は何を目指すべきか
第二章 「主体性」を捉え直す
第三章 子供たちに求められる「能力」
第四章 「探究」の再検討
第五章 何をどこまで学ぶべきか
終章 これからの教育はどこへ向かうか
著者等紹介
白井俊[シライシュン]
1976年生まれ。埼玉県出身。東京大学法学部卒業。コロンビア大学法科大学院修士課程修了。2000年文部省(現・文部科学省)に入省し、同省生涯学習政策局(現・総合教育政策局)、初等中等教育局、高等教育局、国際統括官付等で勤務。その間、徳島県教育委員会、OECD(経済協力開発機構)、独立行政法人大学入試センターに出向。2023年8月より内閣府に出向し、現在、同府科学技術・イノベーション推進事務局参事官(研究環境担当、大学改革・ファンド担当)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
- 評価
-





Hr本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
どんぐり
江口 浩平@教育委員会
ほんメモ(S.U.)
武井 康則
-

- 電子書籍
- 腹黒社長にハメられました【タテヨミ】第…
-
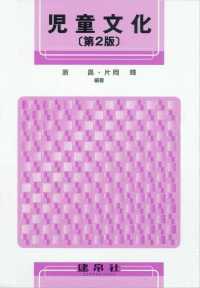
- 和書
- 児童文化 (第2版)