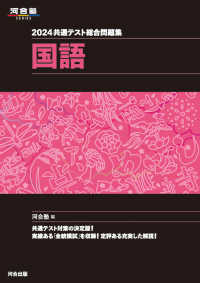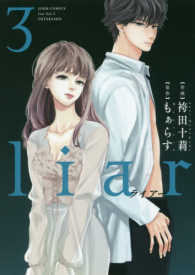出版社内容情報
応仁の乱後、弱体化した室町幕府。将軍は無力だったと言われるが本当か。九代義尚から十五代義昭まで七人のしたたかな戦いを描く。
内容説明
足利将軍家を支える重臣たちの争いに端を発した応仁の乱。その終結後、将軍家は弱体化し、群雄割拠の戦国時代に突入する。だが、幕府はすぐに滅亡したわけではない。九代義尚から十五代義昭まで、将軍は百年にわたり権威を保持し、影響力を行使したが、その理由は何か―。歴代将軍の生涯と事績を丹念にたどり、各地の戦国大名との関係を解明。「無力」「傀儡」というイメージを裏切る、将軍たちの生き残りをかけた戦いを描く。
目次
序章 戦国時代以前の将軍たち
第1章 明応の政変までの道のり―九代将軍義尚と一〇代将軍義稙
第2章 「二人の将軍」の争い―義稙と一一代将軍義澄
第3章 勝てずとも負けない将軍―一二代将軍義晴
第4章 大樹ご生害す―一三代将軍義輝
第5章 信長を封じこめよ―一五代将軍義昭
終章 なぜすぐに滅びなかったのか
著者等紹介
山田康弘[ヤマダヤスヒロ]
1966年(昭和41年)、群馬県に生まれる。学習院大学文学部卒業。同大学大学院人文科学研究科博士後期課程を修了し、博士(史学)を取得。現在、東京大学史料編纂所学術専門職員。専門分野は日本中世史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
134
足利将軍は応仁の乱以後は弱体化し、有名無実化したと思われてきた。しかし9代義尚から15代義昭までの歴代将軍は、腐っても足利というブランドで戦国乱世にも影響力を保持し続けた。訴訟裁定や官位昇進で利用価値をアピールし、国連のような立場で生き残りを図ったと分析する。しかし将軍家は度重なる内紛で自らの足では立てぬほど衰え、名誉だけでなく三代義満のような実権を求めて支援大名を切り捨てるのを繰り返し、遂に信長に滅ぼされた。懸命に戦い続けたのは事実だが、過去の栄光にしがみつき現実直視を拒んだ愚かさに、弁護の余地はない。2023/09/18
ヒロ
83
今までは戦国時代の足利将軍は常に存在感はなく、ただのお飾りでしかなかった印象ですが、今回はそれがことごとく覆されました。特に大名同士の仲を取り持ったり、栄典を与える側として現代の国連の様な役目を負っていたというのは驚きで存在感はとても大きかったんだなと分かりました。そして当然幕府を存続させるために時には戦も行い苦労しながら各将軍が必死に生きていたのが今までのイメージと全く違い、面白かったです。今後はまた違う視点でこの時代を見ていけるんじゃないかと思いました。2023/08/27
skunk_c
75
日本史の時代区分で一番わかりにくいのが室町時代と安土桃山時代。戦国時代はよく使われるけど権力史からいうとちょっと違う。本書はその戦国時代の室町政権(しばしば京都を追われているけど)についてのわかりやすい概説書。現代と繋ぎながらの説明は好感が持てた。また終章の足利将軍が生き残れた理由の解説は理解しやすく、いわゆる歴史書とは異なるセンスを感じた。一方残念だったのは本能寺の変と足利義昭の関連について、「現在までなお明らかでない」と説明を省く。様々な論考があるのだから、その紹介だけでもしてもらいたかったな。2023/10/15
HANA
68
自分の中だと室町幕府は応仁の乱から永禄の変まで飛んでいるのだけど、本書はその間の知識の空白を埋めてくれる一冊。戦国時代に宣下された七人の将軍、本書はその事績を追ったものであると同時に、室町幕府後半の通史としても面白く読める。本書で改めて教えられたのは足利家が直接の戦力を持たず常に守護の軍事力の上に成り立つという事実。中央集権の真逆であるな。戦国物でよく言われる足利義昭の手紙攻勢であるが、あれは特殊なものではなく足利として基本的な戦略だったのだなあ。とあれ限定的な状況で戦った将軍の群像、面白かったです。2023/09/30
kk
48
図書館本。応仁の乱の後、武力等の面では小大名並みの足利将軍たちが百年の風波を凌げたのは何故か、その秘密に迫ろうとする一冊。義尚から義昭まで七代の治績を辿った上、将軍の権威が大名間外交の世界で特有の機能を果たしていた点に注目。戦国期日本の政治状況を現代国際社会における主権国家体制に準えて、足利将軍の役割について今日の国連の機能のアナロジーで説明を試みる。事の当否は兎も角として、ユニークでとっつき易い視点。ミクロな事象への言及は最小限に抑えられ、kkなど一般読者に優しく親切な語り口。2024/01/11
-

- 電子書籍
- スマッシュ 2025年3月号
-
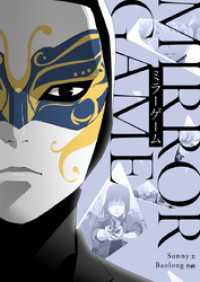
- 電子書籍
- ミラーゲーム【タテヨミ】第5話 pic…