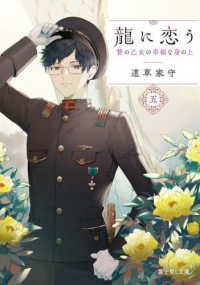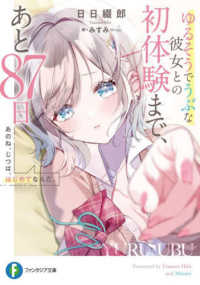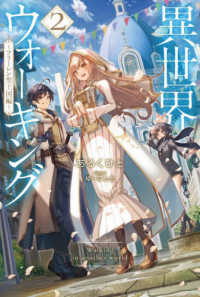出版社内容情報
軍事国家であったチベットはインド仏教を受容し、12世紀には仏教界が世俗に君臨する社会となった。17世紀に成立したダライ・ラマ政権はモンゴル人、満洲人の帰依を受け、チベットはアジアの聖地として繁栄した。しかし、1950年人民解放軍のラサ侵攻によりチベットは独立を失い、ダライ・ラマ14世はインドに亡命した。チベット仏教が欧米社会で高く評価されているため、チベット文化はかろうじて維持されているが、チベットの未来は今後どうなるのか?
内容説明
古代に軍事国家だったチベットはインド仏教を受容、12世紀には仏教界が世俗に君臨する社会となった。17世紀に成立したダライ・ラマ政権はモンゴル人や満洲人の帰依を受け、チベットは聖地として繁栄する。だが1950年、人民解放軍のラサ侵攻により独立を失い、ダライ・ラマ14世はインドに亡命した。チベットはこれからどうなるのか?1400年の歴史を辿り、世界で尊敬の念を集めるチベット仏教と文化の未来を考える。
目次
序章 仏教国家チベットの始まり
第1章 古代チベット帝国と諸宗派の成立
第2章 ダライ・ラマ政権の誕生
第3章 ダライ・ラマ十三世による仏教界の再興
第4章 ダライ・ラマ十四世によるチベット問題の国際化
終章 現代の神話、ダライ・ラマ十四世
著者等紹介
石濱裕美子[イシハマユミコ]
1990年、早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得。早稲田大学教育学部専任講師等を経て、早稲田大学教育・総合科学学術院教授。博士(文学)。専攻、チベット仏教世界(チベット・モンゴル・満洲)の歴史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
榊原 香織
サアベドラ
kk
さとうしん