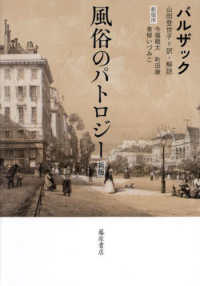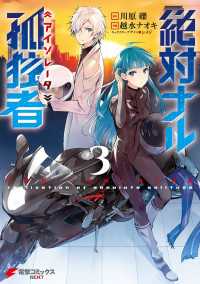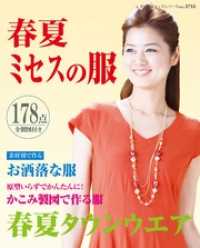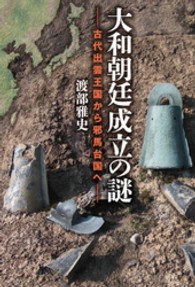出版社内容情報
「問・母とは二度会ったが、父とは一度も会わないもの、なーんだ?」(答・くちびる)。この室町時代のなぞなぞから、当時「ハハ」は「パパ」のように発音されていたことがわかる。日本語の発音はどのように変化してきたのか。奈良時代には母音が8つあった? 「平」を「ヘイ」と読んだり「ビョウ」と読んだり、なぜ漢字には複数の音読みがあるのか? 和歌の字余りに潜む謎からわかる古代語の真実とは? 千三百年に及ぶ音声の歴史をたどる。
内容説明
問題「母とは二度会ったが父とは一度も会わないもの、なーんだ?」(答・くちびる)。この室町時代のなぞなぞから、当時「ハハ」は「ファファ」のように発音されていたことがわかる。では日本語の発音はどのように変化してきたのか。奈良時代には母音が8つあった?「行」を「コウ」と読んだり「ギョウ」と読んだり、なぜ漢字には複数の音読みがあるのか?和歌の字余りからわかる古代語の真実とは?千三百年に及ぶ音声の歴史を辿る。
目次
序章 万葉仮名が映す古代日本語音声―唐代音からの推定
第1章 奈良時代の音声を再建する―万葉びとの声を聞く
第2章 平安時代語の音色―聞いた通りに書いた時代
第3章 鎌倉時代ルネサンスと仮名遣い―藤原定家と古典文学
第4章 宣教師が記録した室町時代語―「じ」「ぢ」、「ず」「づ」の合流と開合の別
第5章 漢字の音読みと音の歴史―複数の読みと日本の漢字文化
第6章 近世の仮名遣いと古代音声再建―和歌の「字余り」から見えた古代音声
著者等紹介
釘貫亨[クギヌキトオル]
1954年、和歌山県生まれ。1982年、東北大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。1997年博士(文学)・名古屋大学。1982年、富山大学人文学部講師、1987年、同大学助教授、1993年名古屋大学文学部助教授、1997年同大学教授、2000年同大学大学院文学研究科教授。名古屋大学名誉教授。専攻、日本語学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。