出版社内容情報
後鳥羽上皇は無謀にも鎌倉幕府打倒を企て、返り討ちにあったのか? 公武関係を劇的に変え、中世社会のあり方を決めた大乱を描く。
坂井孝一[サカイコウイチ]
著・文・その他
内容説明
一二一九年、鎌倉幕府三代将軍・源実朝が暗殺された。朝廷との協調に努めた実朝の死により公武関係は動揺。二年後、承久の乱が勃発する。朝廷に君臨する後鳥羽上皇が、執権北条義時を討つべく兵を挙げたのだ。だが、義時の嫡男泰時率いる幕府の大軍は京都へ攻め上り、朝廷方の軍勢を圧倒。後鳥羽ら三上皇は流罪となり、六波羅探題が設置された。公武の力関係を劇的に変え、中世社会のあり方を決定づけた大事件を読み解く。
目次
序章 中世の幕開き
第1章 後鳥羽の朝廷
第2章 実朝の幕府
第3章 乱への道程
第4章 承久の乱勃発
第5章 大乱決着
第6章 乱後の世界
終章 帝王たちと承久の乱
著者等紹介
坂井孝一[サカイコウイチ]
1958年(昭和33年)、東京都に生まれる。東京大学文学部卒業。同大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得。博士(文学)。専攻、日本中世史。現在、創価大学文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
夜間飛行
205
新古今和歌集の編纂に深く関わり、最勝四天王院の障子に全国歌枕の絵と歌を集めさせた後鳥羽院。その旺盛な活動は常に《幻想の帝国》への夢から発していた。践祚時に宝剣が欠けていたことがこの帝の生涯に大きな影を投げかけていたのだという。承久の乱の目的も倒幕ではなく、王としての統治=公武合体の実現を阻む義時の討伐にあった。乱後、保元以来65年に及ぶ戦乱を振り返る気運が高まり、保元物語、平治物語、平家物語の原型が作られた。平知盛に養育された守貞親王とその子後堀河の宮廷に、平家ゆかりの人々のコミュニティが復活したらしい。2023/03/19
KAZOO
124
中公新書の中世の乱シリーズ(応仁の乱、観応の擾乱に続く)の3冊目で、今回は武家社会が確立した乱を分析しています。このような本がよく読まれているなあと思っています(かくいうわたしもその一人ですが)。あまり乱のようなことが起きていない時代だからこそ読まれているのかもしれません。さらっと読んだだけですが、今までせいぜい高校時代の日本史(数ページ)でしか知らなかったことが詳しく書かれています。2019/02/08
buchipanda3
104
大河ドラマもいよいよ最後の見せ場へ。その仕上げの一つとなる承久の乱について、ドラマの時代考証を担う著者の本を読んでみた。鎌倉と後鳥羽上皇の対立はどういった流れで生じたのか。カギとして上皇と実朝が望んだ統治構想を丁寧に読み解いていたのが興味深かった。正統な王たる理想像を追求した上皇、幕府内院政を目指した実朝。二人の構想は同じ方向で、義時も尽力する。しかし事件が起きて頓挫(著者は義時黒幕説を否定)。理想が潰え、後は両陣営の思惑は噛み合わず決戦へ。一つの出来事が大きく左右することに改めて歴史というものを感じた。2022/10/10
Willie the Wildcat
88
後鳥羽上皇と実朝の描いた夢のための(倒幕/討幕ではなく)義時追討。心底に、正当な王としての自負。宮廷儀礼の復興推進にも直結。故に印象的なのが、「草薙の剣」の件。追討院宣・官宣旨の首尾良ければ、という”タラれば”はあるが、「チームvs.カリスマ」と、実戦経験の有無が勝敗の分かれ目。加えて、黒幕・政子と汚れ役・義村の”表裏”の右腕の存在も両、陣営の差異。地頭改補を要求する院宣の幕府却下は、大きな転機の1つという感。読後、隠岐の島でも威厳を保とうとする上皇の歌、そして実朝の”罪”の歌の意味に深みを感じる。2021/12/15
k5
85
小学生の頃、歴史漫画で「頼朝殿の恩は山よりも高く、海よりも深い」という北条政子の演説を読んだ時は、オバハン厚かましいなあ、と思ったのですが、社会に出て、思うことを思うように言えなくなってみると、この演説の凄さが分かります。なにしろ上皇が自分の弟の追討令を出し、いつ裏切るか分からない武家たちに囲まれて言ったのですから。さて本書は院政の成立から語り起こして、実朝の死、乱の勃発まで大きな視点で書いてあってとても読みやすいです。また、後鳥羽上皇と政子の指揮官としての器の違いなども見えてきます。2021/10/08
-
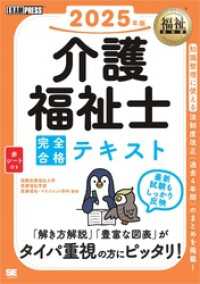
- 電子書籍
- 福祉教科書 介護福祉士 完全合格テキス…








