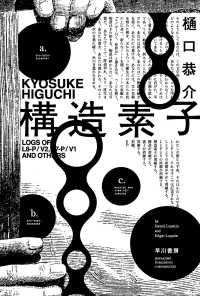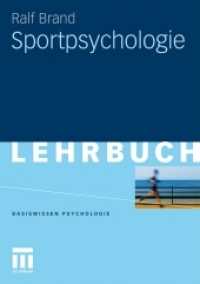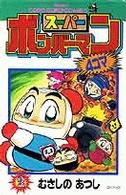出版社内容情報
俗世間を離れ、自らの心の内を見つめ、修練をはかる修道院。12世紀、突如としてその伝統から大きく離れた修道会が生まれた。騎士修道会と托鉢修道会である。かたや十字軍となって聖地や北方、イベリア半島で異教徒と戦い、かたや都市のただ中で貧民の救済にラディカルにつとめた。これら「鬼子」ともいうべき修道会はなぜ生まれ、どのような行路をたどったのか。各修道会の戒律や所領経営などにも注目しながら通観する。
内容説明
俗世間を離れ、自らの心の内を見つめる修道院。だが12世紀、突如その伝統から大きく離れた修道会が生まれた。騎士修道会と托鉢修道会である。かたや十字軍となって聖地エルサレムやイベリア半島、北方で異教徒と戦い、かたや聖フランチェスコらが都市のただ中で民衆の信仰のあり方をラディカルに変革した。これら“鬼子”ともいうべき修道会の由来と変遷を、各修道会の戒律や所領経営などにも注目しながら通観する。
目次
第1章 十字軍遠征と騎士
第2章 騎士修道会の戒律
第3章 国際金融と所領経営―テンプルとホスピタル騎士修道会
第4章 国家としての騎士修道会―ドイツ騎士修道会
第5章 レコンキスタの旗の下に―イベリア半島の騎士修道会
第6章 ヨーロッパの都市化と富の行方―托鉢修道会の出現
第7章 聖フランチェスコの革新
第8章 異端告発と学識者―ドミニコ修道会の役割
第9章 修道院の外で―ベギン派が映すもの
著者等紹介
佐藤彰一[サトウショウイチ]
1945年山形県生まれ。1968年、中央大学法学部卒、1976年、早稲田大学大学院博士課程満期退学。名古屋大学教授等を経て、同大学名誉教授。日本学士院会員。『修道院と農民―会計文書から見た中世形成期ロワール地方』により日本学士院賞受賞。専攻・西洋中世史。博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かごむし
hide
こぽぞう☆
MUNEKAZ
羊山羊
-

- 和書
- 竹取物語 学燈文庫