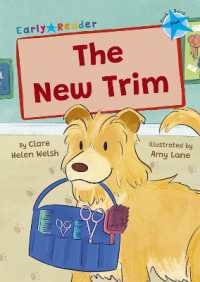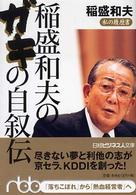出版社内容情報
ヒトは食糧をどうやって獲得してきたか。東洋の「コメと魚」、西洋の「パンとミルク」に代表される、糖質とタンパク質のセットを探る。
内容説明
人は食べなければ生きていくことはできない。人類の歴史は、糖質とタンパク質のセットをどうやって確保するかという闘いだった。現在、西洋では「麦とミルク」、東洋では「コメと魚」の組み合わせが一般的だ。だが、日本を例にとっても山菜を多食する採集文化が色濃く残っているように、食の営みは多様である。本書は、ユーラシア全土で繰り広げられてきた、さまざまな「生業」の変遷と集団間の駆け引きを巨細に解読する。
目次
第1章 人が生きるということ
第2章 農耕という生業
第3章 アジア夏穀類ゾーンの生業
第4章 麦農耕ゾーンの生業
第5章 三つの生業のまじわり
終章 未来に向けて
著者等紹介
佐藤洋一郎[サトウヨウイチロウ]
1952年、和歌山県生まれ。1979年、京都大学大学院農学研究科修士課程修了。高知大学農学部助手、国立遺伝学研究所研究員、静岡大学農学部助教授、総合地球環境学研究所教授・副所長等を経て、大学共同利用機関法人人間文化研究機構理事。農学博士。第9回松下幸之助花と緑の博覧会記念奨励賞(2001)、第7回NHK静岡放送局「あけぼの賞」(2001)、第17回濱田青陵賞(2004)受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
53
ユーラシア大陸に限るとはいえ、人類が誕生してからどのように食料を確保してきたか、その壮大な歴史の前にめまいがしそうな浪漫を感じた。また、これからの資源としての食糧の在り方を改めて考えた。平易な文章で書かれているので理解しやすい。2016/06/26
bapaksejahtera
15
DNA分析による遺伝学的手法を用いた、日本の稲の来歴に関しユニークな知見を明らかにした著者の本には、大いに感銘を受けた物である。最近の著作は文明論的方向に傾いたようで、本書もその流れにあり、人類の生業として農耕、遊牧、漁労を含む狩猟採集の三つを挙げ論ずる。人が生きる為には蛋白と糖質の確保が必須であり、その為に三つの生業に掛る民の其々が、相互に何らかの連関を図った歴史が述べられ、夏作の稲・雑穀圏、冬作の種々の麦作圏のあり様や歴史、遊牧地帯の希薄な土地所有意識の由来等、示唆的な記述が多いが纏まりには乏しかった2025/11/17
おはぎ
13
人類が「いかに食べてきたか」探る本。「だろう」も多くはっきりとしないところもあるが、その分古来からのダイナミックさを感じられる。中国での小麦の受け入れられるまでの過程など専門で読みたくなった。また、魚の養殖が農耕の初期段階に対応しているという視点は新鮮だった。2024/06/04
Takayuki Oohashi
13
普段読まないタイプの本ですが、SSを書くにあたって東西の食の違いというのは非常に重要だと思い、読んでみました。アニメ「山賊の娘ローニャ」で、古城の中でローニャ達が鶏や豚を飼い、ソーセージにして貯蔵するシーンや、アニメ「精霊の守り人」で、バルサやチャグムが屋台で麺を食べるシーンが、それぞれ欧州と東南アジアの食文化を正確に再現しているということが、この本を読んで分かったような気がします。「食」のことを総合的に書いたかというと疑問ですが、僕の知らない農耕や放牧の話が散りばめられていて、非常に参考になりました。2016/06/06
Francis
10
人類の発祥以来、人類はどの様に食糧を確保してきたのか、ユーラシア大陸を中心に考察。農耕と遊牧との関係の歴史についての考察には目から鱗が落ちるものが多かった。とても面白い。人類がここまで文明化して自然から切り離されてしまっても、所詮我々人類は自然の制約下で生きるしかない生き物にであることを自覚させられる。人類はこれからどうなるのか、考える上でも参考になる本。2016/10/19
-

- 和書
- ポジティブ育児メソッド