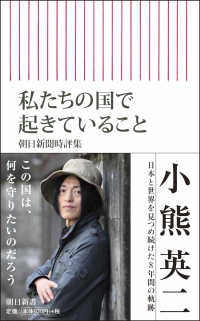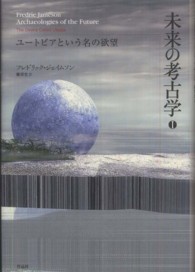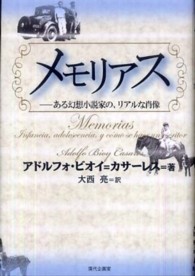内容説明
一神教とは異なり、日本人にとって神は絶対的な存在ではない。山岳や森林をはじめ、あらゆる事物が今なお崇拝の対象となり得る。遠くさかのぼれば、『古事記』に登場する神々は、恋をするばかりか嫉妬もし、時に寂しがり、罪さえも犯す。独特の宗教観や自然観はどう形成され、現代にまで影響を及ぼしているか。「カムナビ」「ミモロ」などのキーワードを手がかりに記紀万葉の世界に分け入り、古代の人びとの心性に迫る。
目次
序章
第1章 神と地名の古代学
第2章 原恩主義の論理
第3章 「モリ」に祈る万葉びとたち
第4章 「カムナビ」と呼ばれた祭場、聖地
第5章 神の帯にする川
第6章 ミモロは人の守る山
第7章 畏怖と愛惜とい感情
第8章 人と天皇と神と
終章
著者等紹介
上野誠[ウエノマコト]
1960年(昭和35年)、福岡県に生まれる。國學院大學大学院文学研究科博士課程後期単位取得満期退学。博士(文学)。奈良大学文学部国文学科教授。国際日本文化研究センター客員教授。研究テーマは万葉挽歌の史的研究、万葉文化論。日本民俗学会研究奨励賞、上代文学会賞、角川財団学芸賞を受賞。オペラや朗読劇の脚本も手がける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
73
「古事記」「日本書紀」「万葉集」を基に7,8世紀の古代の人々にとって聖なるものとは何かを考察している。古事記より日本は神様の性交によって国土が生まれる国。女性神が死ななくては神話が成立しない。万葉集には枕詞と地名を歌に詠み込む伝統があった。枕詞は土地の由来を語る神々の物語。日本の宗教には、特定の神仏に対する信仰よりもその場・土地に身を委ね神や霊を感じることが大切であり、経典や教理など不要なのだということに納得がいく。1300年経つ我々に古来の文化が継承されているのか?著者の指摘はもっともである。2019/10/14
Shoji
58
要するに「アニミズム」について書かれています。万葉集が書かれた時代である奈良時代に生きた人々の心性や生活の様子を、万葉集から読み解いています。その過程で行き着くものは、いや、避けて通れないのがカムナビでありミモロです。万葉人は、「三輪山や大和三山を畏怖しシメ(注連縄など)を結び、聖なるものとした」と読み解いています。奈良県人であり、著者の講演も何度か聞いている私は興味深く読むことが出来ましたが、果たして万人受けする本かどうかは、若干疑問です。2018/04/24
tamami
48
書棚の積ん読本を再読。古代や古代学についての自分の不明を改めて思う。著者は、山川草木全てのものが神になり得る存在であるという。それらの神は、事々しく名を挙げて覚え奉るよりも、神々の住まうその場に行き、古代人の心をもって感じるものかも知れない。「モリ」「カンナビ」という地名についての考察では、自分の住む故郷にも、そんな考察の対象になる地域はないだろうか、などと思いを巡らせた。神一つ取ってみても、現代的、西洋的な見方に囚われがちな我々であるが、万葉古事記等、古典の世界に古代人の心を探る著者の方法に教えられる。2022/02/15
井月 奎(いづき けい)
48
私は優柔不断で梅原猛を読めば「奈良は仏だよなあ」と思い、この本の著者、上野誠を読めば「奈良は神々のおわすところよ」となって、苦笑を禁じ得ないのですがそれもまた楽しいのです。奈良、飛鳥には神仏が絶妙な距離感を保ちつつ同居しているように思いますが、著者は記紀万葉を軸に神々と人の来し方行く末に目を向けます。しかしそれは仏教を排除するものではなく、人が大切にしなければいけないことを神々を通して教えてくれるのです。ニクイ歌を巻末に記しています。「なにごとのおはしますかは知らねども かたじけなさに涙こぼるる」 西行2020/04/13
獺祭魚の食客@鯨鯢
32
皇室による記紀神話は大陸から皇室の祖先が渡来する前から土着の自然崇拝や伝承物語を集大成したものだと推測されます。製鉄や稲作の技術、鏡など武力ではない権威により王化する過程は、ヤマトタケルや四道将軍の派遣、神武東征の物語として象徴的に描かれました。/ 天照や卑弥呼(日巫女)など祭祀を司る巫女は、日や月、山海などの自然神と同列の神の子とすることで聖なる存在になっていきました。2019/06/16