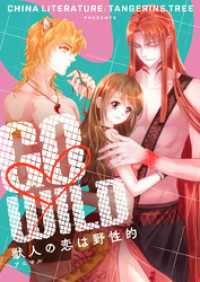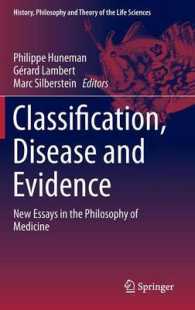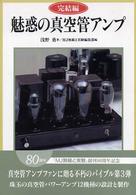内容説明
公家社会と深く交わるなかで王朝文化に精通し、明国の皇帝には日本国王の称号を授与され、死後、朝廷から太上天皇の尊号を宣下される―。三代将軍足利義満の治世はしばしば「皇位簒奪」「屈辱外交」という悪評とともに語られる。だが、強大な権力、多様な事績に彩られた生涯の全貌は、いまだ明らかにはなっていない。本書では、新史料にも光を当て、公武に君臨した唯一無二の将軍の足跡をたどる。
目次
第1章 室町幕府と北朝
第2章 右近衛大将という地位
第3章 武家にして内大臣
第4章 室町将軍の学識
第5章 寵臣と稚児
第6章 地域権力の叛乱と掌握
第7章 応永の乱と難太平記
第8章 北山殿での祭祀と明国通交
第9章 太上天皇宣下をめぐる思惑
終章 妻妾と女房について
著者等紹介
小川剛生[オガワタケオ]
1971年東京都生まれ。慶應義塾大学文学部国文学専攻卒業、同大学院博士課程中退。熊本大学助教授を経て、国文学研究資料館助教授、2007年准教授、2009年慶應義塾大学文学部准教授。2006年、『二条良基研究』で角川源義賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mitei
47
しかし室町時代って中々資料も少ないし歴史的には重要だけど幕末ほど話題性もないしいつも不思議な時代だなぁと感じる。2012/09/19
ぴー
42
本書で義満の人物像を概ね把握。早い時期から公家社会を知り、仏教勢と深く交流していたことも知った。また将軍として、外様勢力削減の緻密な計画と、最終的に今川氏を不憫に扱ったのは権力者らしいと感じた。自分は義満の皇位簒奪は初耳だったが、否定されているのだろう。明との貿易も利益確保のみが目的だったと理解。筆者も外交面を評価している。晩年、太上天皇の望みを公家から一蹴されるところが、少し切ない。歴代将軍に無知ですが、この時期だけを見ると、義満は少なくともカリスマ性を持っていたのではないでしょうか。 2024/10/04
Toska
26
文字通り「公武に君臨した」足利義満だが、寧ろ「公」の部門での成功が大きかったという印象。それは公家たちが進んで彼を担いだからに他ならず、とりわけ関白・二条良基との二人三脚っぷりは本書の読みどころの一つ。衰微した朝廷を立て直すには将軍の力が不可欠で、義満も敢えてこれに乗り、結果として絶大な権力を手に入れた。根拠薄弱な皇位簒奪説に頼らずとも、日本史上稀に見る巨頭であったことは間違いない。2025/05/25
takeapple
26
国文学研究資料館にいらした小川剛生さんの著書だけあって、当時の日記や写本、文書の細かなところまで読み込み、義満の実像に迫る記述は実証主義文献史学の王道と言うべきもの。反面というかそのためというか、政治史の細部には詳しく、一世を風靡した、義満による皇位簒奪等を論破した価値は大いに認められるが、義満の実像に迫るには、他の義満伝も合わせて読む必要があると思う。網野善彦の時代に中世史に興味を持った私には物足りなかったが、著者の厳格な史料批判は素晴らしいと思う。ただ難しい漢語や古語が普通に使ってあるのがどうかな。2018/03/21
coolflat
20
義満期における政治史や美濃の乱(土岐康行の乱)~明徳の乱(山名氏清の乱)~応永の乱(大内義弘の乱)に至る義満の権力確立過程を詳しく知りたかったが、本書の半分は、義満の文化・芸術面における功績や義満の公家的性格を記述したものだったので、個人的には消化不良だった。155頁。関東の大乱、永享の乱~享徳の乱の遠因。管領職の任命は、一貫して公方ではなく将軍の支持によるものであった。関東管領は将軍の意を受け公方を掣肘する働きを期待された。公方と管領は同床異夢であり、君臣水魚の間柄が不信と憎悪に終わることも多かった。2020/05/10