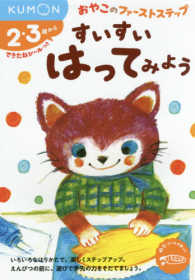内容説明
徳川の世は泰平。人びとはどこへでも旅ができる喜びを実感する。旅といえば辛く悲しいという中世以来の意識は劇的に変化し、「楽しい」「面白い」が紀行文の一つの型となり、さらに「いかに実用的か」が求められるようになる。辺境への関心も芽生え、情報量も豊富になっていく。好奇心いっぱいの殿様の旅、国学者のお花見、巡検使同行の蝦夷見聞などを通して、本書は江戸の紀行文の全体像を浮かび上がらせるものである。
目次
第1章 『おくのほそ道』は名作か?
第2章 林羅山と名所記―『丙辰紀行』を読む
第3章 石出吉深と寺社縁起―『所歴日記』を読む
第4章 貝原益軒と博物学―『木曾路記』『南遊紀事』を読む
第5章 本居宣長と古典文学―『菅笠日記』を読む
第6章 橘南谿と奇談―『東西遊記』を読む
第7章 古川古松軒と蝦夷紀行―『東遊雑記』を読む
第8章 土屋斐子と女流紀行―『和泉日記』を読む
第9章 東海道の紀行はなぜつまらないのか?
第10章 小津久足と旅心―『青葉日記』を読む
終章 その後の紀行―幕末から明治へ
著者等紹介
板坂耀子[イタサカヨウコ]
1946年(昭和21年)、大分県に生まれる。九州大学文学部、同大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。熊本短期大学講師、愛知県立短期大学講師、助教授、福岡教育大学助教授、教授を経て、福岡教育大学名誉教授。博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
gorgeanalogue
10
各地の事実を事実として報告しようとする態度と文学的に過去に陶酔する態度。または俗化した名所を嘆く態度。さらにはまた荒唐無稽な文物や現象をエンターテイメントばりに面白おかしく語る態度。いくつか類型化される江戸の紀行文の中で、土屋斐子「たびの命毛」「和泉日記」に惹かれた。ロマンティックな過去への思慕と現在の平凡な自分の生活とを冷静に観察する斐子の態度は、擬古文という文体も相まって、いってみれば樋口一葉にも通ずると感じられる。2025/05/25
bapaksejahtera
9
近世紀行文は近年迄「奥の細道」への一辺倒の評価によって多くの作品が無視され埋もれてしまい、活字化しない作品も多い。江戸期に入って多くの人々が旅行を楽しむ時代が訪れる。人々からは旅の導きとなる情報が求められた。しかし上記書は江戸以前の紀行文学に仮託し、都を離れ辺地に旅立つ憂愁と怖れを詩的に歌い上げる虚構に満ちた文学であり、上述の需要には対応し得ない。本書は、著者に至る紀行文学研究者の間で事実に正確で旅の実用になる紀行文学として高い評価を得、併せて江戸期に屡々利用された、林羅山貝原益軒橘南谿等の作品を紹介する2025/03/27
犬養三千代
6
2011年1月25日 板坂燿子 880円 珍しく自家本。第8章の 土屋廉直の妻拏子の和泉日記に興味を持った。何故 擬古文なのか? また、江戸の蝦夷地探険 第7章の古川古松軒の東西雑記も。一度しらべて見よう。2018/12/21
すのさん
5
『おくのほそ道』は江戸以前の緊張感と悲壮感のある旅を再現した点に特徴があり、中世以前の名作紀行の伝統を受け継ぐ。その点で、既に旅が娯楽化し始めていた「江戸時代の」紀行文の名作とは言い難い。江戸の紀行文は土地の情報、旅の楽しさが伝わるような作品を通しての明るさ、正確で明快な表現が求められていた。貝原益軒、橘南谿、古川古松軒、本居宣長など近世紀行文の代表的作家を章ごとに挙げ、各作品を取上げるが、以上の三点をどの作品も共通して持つ。情報の精度など細かい点に関しては違いがあり、そこに作者の個性が現れている。2021/01/25
みみずばれ
4
タイトルや装丁から堅そうな印象を受けるが内容はとても読みやすい。読んでいるうちに「江戸の紀行文」だけでなく、現代のものも含めた紀行文全般に興味がわいてしまった。現代の旅はどうしても車や電車や飛行機などの利用が前提にあり、例え徒歩の旅の記録を書いたとしても、それは乗り物中心の社会の中を歩いた記録にならざるを得ない。そう考えると、みんなが歩いていた時代の旅の記録はこの先書かれることのない貴重なものだし、現代人が読んで新鮮に楽しめる部分も多いのではなかろうか。2011/05/25
-
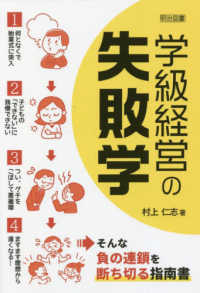
- 和書
- 学級経営の失敗学