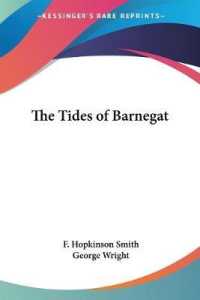出版社内容情報
保守本流を歩み、一九七八年に首相に就任した大平。政界屈指の知性派で自由主義を強く標榜した彼の軌跡を追い、保守政治の意義を問う。
内容説明
戦後、「保守本流」の道を歩み、外相・蔵相などを歴任、一九七八年に首相の座に就いた大平正芳。その風貌から「おとうちゃん」「鈍牛」と綽名された大平は、政界屈指の知性派であり、初めて「戦後の総決算」を唱えるなど、二一世紀を見据えた構想を数多く発表した。本書は、派閥全盛の時代、自由主義を強く標榜し、田中角栄、福田赳夫、三木武夫らと切磋琢磨した彼の軌跡を辿り、戦後の保守政治の価値を問うものである。
目次
序章 「戦後の総決算」の主張
第1章 青少年期―人間と思想の形成
第2章 「保守本流」の形成―宏池会の結成
第3章 宰相への道―「三角大福」派閥抗争の時代
第4章 大平政権の軌跡
終章 「含羞」の保守政治家
著者等紹介
福永文夫[フクナガフミオ]
1953年(昭和28年)兵庫県生まれ。76年神戸大学法学部卒業、85年神戸大学大学院法学研究科博士課程単位取得満期退学。87年姫路獨協大学専任講師就任。同大学助教授、教授を経て、2001年から獨協大学教授。博士(政治学)。専攻、日本政治外交史・政治学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mitei
33
大平正芳の生涯を書いた本。こういう本に有りがちな生い立ちから死ぬまでを並べただけの一冊でもう少し首相時代の話をして欲しかった。宰相大平正芳までが時代のターニングポイントになっているように感じた。2011/08/08
ふみあき
30
中曽根康弘や田中角栄らと比べると、大平正芳は良くも悪くも突出した部分がないため、いかにも地味に思えるけど、そこに彼の本領がある。「首相にリーダーシップは不要」と言い切るほどに強権を忌避し、政治を「目的地のない航海」に 喩える。それこそ(設計主義に対置されるものとしての)保守主義の真髄かもしれない。2022/01/12
はやしま
24
大平正芳個人と同時に戦後日本の自民党政権の変遷を追った読後感。前半は丁寧に語られているが、後半、特に田中以降は語り急いでいるように思われ、官僚時代と池田に仕えた時代の印象が強く残った。真面目でよく勉強しており、打ち出された政策は幅広く、実行されていたらどうなっていただろう。他方で実直な大平が政治の世界に入らず官僚職を全うしたらどうなっていたのだろうとも、官僚時代の姿を読みながら考えた。 子供の頃政治というと自民党内の派閥争いという印象だった。そんな時代を資料で見せてくれた一冊でもあった。2017/10/10
coolflat
23
今は、戦後ではない。戦前が始まろうとしているという人がいる。そういう人は、現在の自民党がかつてのような“戦後保守”を体現する政党でなくなったことが起因と見ている。戦後保守とは何か。戦後保守、いわゆる保守本流とは何かを大平の生涯を通して探っている。保守本流とは、護憲と日米安保を共存させることで、一方で改憲再軍備を唱える自民党内“戦前派”を、他方で護憲日米安保反対を唱える野党を抑える必要から生まれた巧妙な政策路線である。大平の歩みは、吉田の軽軍備経済主義を継承し、保守本流として演出し定着させていく過程であった2018/11/05
寝落ち6段
20
戦後の日本を立て直そうとした政治家。映像で大平を見ると、「あー」と考えながら話しているのがわかる。大変、理知的な政治家だったのだろうと思っていた。実際に、実直で気骨があり、国民のことを考えていたのだろう。大平の生涯を通して、世情やそれに政治がどう対応しようとしたのかが、とてもわかりやすい内容になっていた。一方、派閥の良性が徐々に悪性に変わっていく様、政治資金規正法の問題など現在に至る諸問題の始まりも描かれている。「戦後保守」という戦前を引きずらない、今と未来を見据えた人だったのだろう。2024/06/10
-

- 洋書
- Цеl…