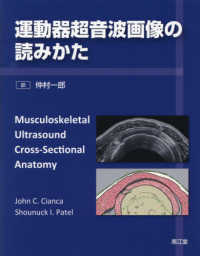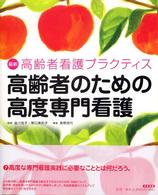出版社内容情報
19世紀半ばから20世紀初頭まで、来日した西洋人たちは、日本の「音」をどのように聴き、感じ、記録したのか
内容説明
イザベラ・バード、エドワード・モース、ピエール・ロチ、ラフカディオ・ハーン、ポール・クローデル…。幕末維新の開国後、数多くの西洋人たちが来日し、彼らの文明とは違う特異な「東洋の島国」が響かせる音に耳を傾けた。日常生活の雑音から日本人が奏でた西洋音楽まで、彼らはどういった音に興味を示し、そこに何を感じ、それをどう記録したのか。十九世紀半ばから二十世紀初頭までの近代日本の音を辿る。
目次
序章 幕末の音風景
第1章 騒音の文化―イザベラ・バードとエドワード・モース
第2章 蝉と三味線―ピエール・ロチ
第3章 “共鳴”の持つ意味―ラフカディオ・ハーン
第4章 始源の音を求めて―ポール・クローデル
終章 変化する音環境
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
びっぐすとん
16
図書館本。明治から昭和初期に日本を訪れた外国人が聞いた日本の音について。写真やスケッチで見たものは記録出来るが、当時実際に街で耳にした生活の音は残ってない。当時の日本は相当騒々しかったようだ。私達が東南アジアの街頭に感じる賑やかさに近いのだろうか?日本に対して好意的かどうかでも印象は違うようだ。三味線の音など今ではもう街中で耳にすることもない、昔と変わらないのは蝉の騒々しさくらいだろうか。当時既に多くの外国人が日本人以上に危惧していたように、急速な欧米化で江戸時代までの日本の暮らしは消え失せてしまった。2021/01/15
キムチ
7
明治初期から中期にかけて、日本を訪れ、日本人女性と関係をもつ事によって文化に親しくした西洋人から感じた印象を「音」に拘って掘り下げる試み。 日本の近代化プロセスが面白いのでので考えるヒントにでもなればと思ってがきっかけ。 モース(近代化を背景とした日本と西洋の交差点に立っていたが故の戸惑い)の心象風景はおぼろげにわかった。次のロチが今一つ。お菊さん、お梅さんと(読んだことないが)日本を題材に描いた小説での彼の立場説明がむにゃむにゃ。言っている事が整理付いていない感じ。 2013/09/09
oooともろー
3
明治時代に来日した西洋人たちが聞いた日本の様々な音。ロチとハーンなど、真逆の感じ方をしているのが面白い。これまで考えたことが無かった視点。2025/03/01
志村真幸
1
著者はフランス文学の研究者。 本書は、明治期に来日したフランス人やイギリス人の残した記録から、「音」に関する記述を分析したもの。 とりあげられているのは、バード、モース、ロチ、ハーン、クローデルなど。 三味線、蝉の声、能の音楽、新設された軍楽隊、宿屋での隣室の酒盛りの声、舞踏会など。 外国人たちの反応もさまざま。騒音だと非難したり、よくわからないながらも味わったり。 分析方法は文学研究的で、音の描写がどのような効果や意味をもつのか論じられており、興味深い。 日本への西洋音楽の浸透についても。2019/03/19
しょうたろうさん
1
○2013/09/01
-
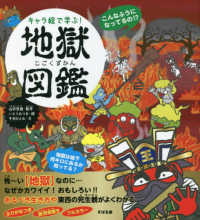
- 和書
- キャラ絵で学ぶ!地獄図鑑