出版社内容情報
騒動が幕府に露見すれば御家断絶、は本当か? 様々な御家騒動を検証し、従来の定説をくつがえす。
内容説明
大名家の相続争いや君臣対立に端を発する御家騒動は、講談・歌舞伎などの格好の題材として庶民の関心を集めてきた。その影響力は甚大で、家中の内紛が幕府に露見すれば即、取り潰しという固定観念が一般に流布する。だが、騒動の実情はそれほど単純だったのだろうか。本書では、黒田・伊達・加賀の三大騒動をはじめ、主要な御家騒動を丹念に検証。下剋上から泰平へという社会変動に着目し、幕藩関係のあり方を捉えなおす。
目次
第1章 近世武士の主従観念と「御家」(多様な主従関係;武士団と家臣団 ほか)
第2章 主君を廃立する従臣たち(鍋島騒動;幼少とは何歳までか ほか)
第3章 従臣を排除する主君たち(「狂気」に走る大名;横田内膳の誅伐事件 ほか)
第4章 主君を選り好みする従臣たち(後藤又兵衛の出奔;堀尾吉晴の牢人再就職の斡旋 ほか)
第5章 御家騒動の伝統化(外様大名取り潰し政策の真否;将軍家の「御一門払い」 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
harass
64
歌舞伎や講談の題材ででてくるお家騒動、江戸時代の藩での内紛を当時の資料などから実態と幕府の対応を解説する新書。通説、主にテレビドラマや映画の時代劇ものでありがちな、君主の絶対的な忠誠とは違い、戦国の下克上の精神を持つ武士たちは上の君主たちが無能な場合は、逃げるか君主の追い落としが珍しくなく、不和や騒動というのは全国で頻発していたという。騒動を対処する幕府側が時代を進むごとに変化していくことも解説。やや硬いがなかなか興味深い内容だった。特に善玉悪玉で分かりやすい創作と実際の違いを痛感。良書。2018/01/04
金吾
26
御家騒動をいくつかの視点から書いています。「主君を廃立する従臣たち」「従臣を排除する主君たち」「主君を選り好みする従臣たち」は面白かったです。2023/12/03
kokada_jnet
19
実証的な江戸初期・中期の御家騒動の研究本。フィクションとしての御家騒動は、実像とあまりにずれているので、この本ではほとんど言及されていない。フィクションに影響されている当方としては、「どちらが悪かったのだろう」とつい考えてしまうのだが、その点はニュートラルで正邪判断はされていない。2016/06/14
浅香山三郎
10
歌舞伎や実録ものを通じて流布した御家騒動について、中世から近世への主従関係のあるべき像の変化を追ふ形で、実態を検証する。戦国期迄の「渡り奉公」といふ行動様式を基底とし、主人である大名の権威が絶対的でない近世初めの大名家中で、有力家臣の出奔、徒党化による内紛が頻発する。通説とは異なり、幕府が公儀に逆らはない限り、さうした藩を積極的に取り潰さうとはしてゐなかつたといふ。後世になり、近世初期の御家騒動が語られるやうになる際、複雑に家臣の忠義を設定せねばならぬ程、その意味が不明瞭に意識されてゐたと言ふのも面白い。2016/12/14
穀雨
7
江戸時代のお家騒動を「主君を排除しようとする従臣」「従臣を排除しようとする主君」など、いくつかのタイプに分類した上で、個別事例を数頁ごとに簡潔に紹介している。ほとんどのお家騒動が収録されているので、一種の事典として手元においておくと便利だと思う。主君としては、高名・有能な従臣に家中から去られることは、自らの無能を世間にさらすという点で面目をつぶされることを意味したという指摘は興味深かった。2022/03/15
-
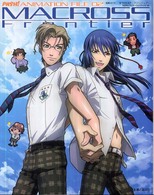
- 和書
- マクロスF 生活シリーズ




