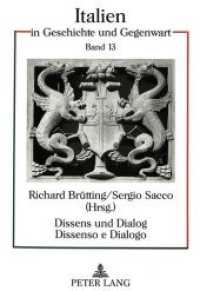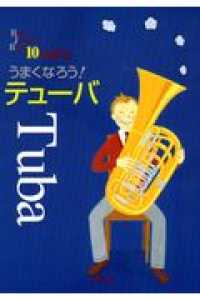内容説明
いま地球上から、二週間に一つのペースで言語が消滅している。英語やスペイン語など優位言語の圧力で消えてゆくものもあれば、話者が激減してうまく継承されない言語も多い。歴史や民族的独自性を表現する言語が死ぬということは、人類の知的遺産の喪失を意味し、世界の多様性を脅かすものである。現在、危機に瀕している言語は六〇〇〇前後といわれる。危機言語を守るために、できること、そしてなすべきこととは何か。
目次
第1章 言語の死とは何か
第2章 なぜ放っておいてはいけないのか
第3章 なぜ言語は死ぬのか
第4章 どこから始めるべきか
第5章 何ができるか
著者等紹介
クリスタル,デイヴィッド[クリスタル,デイヴィッド][Crystal,David]
1941年、北ウェールズ生まれ。ロンドン大学ユニヴァーシティ・カレッジで英語学を専攻。現在、ウェールズ大学バンガー校の言語学科名誉教授
斎藤兆史[サイトウヨシフミ]
1958年、栃木県生まれ。東京大学文学部卒業。同大学院人文科学研究科英語英文学専攻修士課程修了。現在、東京大学大学院総合文化研究科助教授
三谷裕美[ミタニヒロミ]
1965年、福岡県生まれ。1988年、東京女子大学英米文学科卒業。1994年、イリノイ大学修士課程修了。東京女子大学嘱託講師などを経て、現在、ニューカッスル大学博士課程在籍中。専門は言語政策、応用言語学
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ネムル
14
多和田葉子→エコラリアスの繋がりから読む。言語の消滅に対して危機感とまでは言えずも、問題意識には同意こそすれ、では何が出来るのかという問題には距離を感じる。うまく接続出来ない。この本が言語学者として外からの、または上から目線視点で描かれていることも一因だが、結局は経済の問題じゃないかとの諦感がある。ただしいまの政治のお寒い言語活動を見るに、使用される分野が減るごとに言語が、または社会の多様性が衰亡するという点に納得。一番大事なのは他者の言語を抑圧しないことではないかと、とりあえず消極的な読み方で終える。2019/05/21
びっぐすとん
14
期待していたような内容ではなかったので読むのに数日かかった。英語話者の余裕のような「英語は消滅しない、世界言語の地位は揺るがない」という雰囲気がした。保護は大事だけど、そもそも少数言語が絶滅の危機にあるのは英国始め大国が侵略したり、キリスト教布教の際に現地の言葉を蔑ろにしたからじゃないの?そこに二言語併用の余地は無い。ナナメな見方をすれば「どの口がそれを言うかな?」という感じも多少する。言語のみならず人種、宗教など現代は多様性に不寛容な社会で、この事がいずれ人類そのものの消滅に繋がるかもしれない。2019/05/09
Nobu A
12
デビット・クリスタル著書の翻訳版。04年刊行。現在、地球上に6千語が存在し、2週間に1言語の割合で消えている現状。英語帝国主義や二言語併用等、言語使用問題に及び、危機言語を守る為に出来る、すべきことを筆者が提言。一方で「いかなる記録もなされなかった言語が死ぬと、それはまるでもともと存在しなかったのと同じことになる」とあるが、人間だって記録に残るのは著名人のみ。その他大勢は消えてなくなる。国内でもアイヌ語保存運動が起きているが、どこまで介入すべきかは限られた予算等もあり悩ましいところ。パラパラ斜め読み読了。2023/03/17
takao
3
ふむ2022/11/09
KtSwmq
2
危機言語の現状、その保全について論じられている。現在世界には5000~7000程の言語が存在し、半分は21世紀中に失われるらしい。言語を保全するべき理由については本書だけではなかなか釈然としなかった。特に第二章は、「言語保全=(文化・民族的な)多様性の維持」といったように、あくまで言語を文化の一部とみるような見解に貫かれているようにも感じる。異なる言語が複数存在する意義について、文化的観点以外から考えてみる余地はありそうだ。2021/10/10