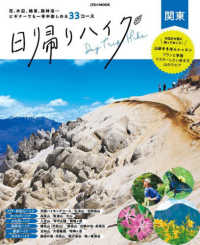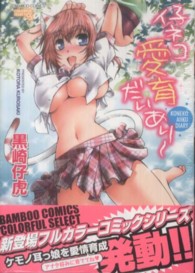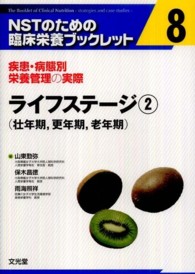内容説明
ドイツの町には、おどろくほど個性がある。通りや建物、広場から、民家の屋根や壁の色、窓のつくりにいたるまで、土地ごとに様式があり、みごとな造形美を生み出している。長らく領邦国家が分立していた歴史的背景から、町ごとの自治意識が強く、伝統や風習に誇りを持っている。港町、川沿いの町、森の町、温泉の町―。ドイツ各地をめぐり、見過ごされがちな風物や土地に根ざした人々の息づかいを伝える紀行エッセイ。
目次
1 北ドイツ(リューゲン島;フーズム;リューベック ほか)
2 中部ドイツ(ボン;ケルン;アーヘン ほか)
3 南ドイツ(トリアー;フロイデンシュタット;シュヴェニンゲン ほか)
著者等紹介
池内紀[イケウチオサム]
1940年(昭和15年)、兵庫県姫路市生まれ。ドイツ文学者。主な著訳書に『海山のあいだ』(講談社エッセイ賞)、『ゲーテさんこんばんは』(桑原武夫学芸賞)、ゲーテ『ファウスト』(毎日出版文化賞)などがある
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。