内容説明
J・フォレスタルはウォール街で成功を収めたのち、ナチス・ドイツがパリに無血入城した直後の1940年8月からノルマンディ上陸作戦直前の四四年五月まで海軍次官、47年9月まで海軍長官をつとめ、戦後、陸海空軍が統合されると、アメリカ初代国防長官に任命された。40年代を通じて「国防の最前線」にあった男が国防長官になったとき担わなければならなかったのは、「安全保障国家」という、矛盾に満ちた巨大な怪物であった。
目次
序章 自殺―ペンタゴンの殉教者
第1章 生い立ち―アイルランド系カトリックの原景
第2章 ウォール街の鬼才―財界での成功
第3章 大海軍の再建―海軍次官時代
第4章 移行期―ローズヴェルト政権からトルーマン政権へ
第5章 冷戦の始まり―反共の闘士
第6章 三軍統合―安全保障国家の青写真
第7章 ペンタゴンの迷宮―初代国防長官の苦脳
終章 フォレスタルの遺産
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
64
初代国防長官が彼だったことは知っていたが、自殺したのは知らなかった。また、公務に就く前はウォール街をブイブイ言わせていたトップビジネスマンだったことも知らず、アメリカの官吏登用システムの凄さを痛感した。彼はやはり戦争という特殊状況の中で、海軍というとりわけ金のかかる組織を発展させるような仕事が向いていたように感じた。特に政治的な余裕を感じさせないストイックな反共主義の持ち主が、戦後の三軍統合という恐ろしくストレスのかかる仕事に取り組まざるを得なかったことが彼の悲劇を生んだようだ。実力者故の運命か。2022/11/17
ジュンジュン
10
戦時下、ローズベルト政権下で、海軍次官・長官を歴任、シビリアンコントロールの一翼を担う。戦後、三軍統合の趨勢のなか、海軍の利益を固守するが、皮肉にも新設の国防長官に就任すると、それが足枷となって本人を苦しめる。突如登極したトルーマンを見て「まったく気の毒な小物」と呟いたフォレスタル。しかし、心を病んだ彼は「可哀そうなフォレスタル、何も決断できなくなってしまった」と、逆にトルーマン大統領に同情される。なんだか彼の自殺は、大企業で働くサラリーマンの悲哀を感じされる。2022/01/15
蟹
3
元同志社大学学長の村田氏、この本の頃はまだ助教授。軍事関係の用語にやや不慣れなところが残るものの、フォレスタルを軸に1940年代の米国の国防・安全保障政策を概観できる良著。フォレスタルを蝕んだのは、まず第一に三軍の権益争いであったという事実、そして海軍の庇護者であった彼が、既得権益を強く主張する海軍に追い詰められていった皮肉が痛ましい。フォレスタルがもし「提督たちの反乱」に直面していたら、いったいどうなっていたのだろう。2016/07/14
ZEPPELIN
3
ルーズベルトの本を読んでいたら、反共と容共で反りが合わない人物として登場したフォレスタル。そんな彼も若かりし頃は共産主義に傾いていたというのは皮肉だが、トルーマン政権となっても意見の対立は消えない。日本と戦いながら国内はこんなにゴタゴタしていたとは、アメリカも凄い国である。海軍長官時代は海軍の利益を守るために、国防省が出来てからは初代の長官としてアメリカの安全保障のために、それぞれ頑張りすぎたということなんだろうか。他国の話とはいえ、こういう死はあってほしくない2015/05/14
富士さん
3
戦後アメリカでの旧国防省と国家安全保障会議事務局との関係にまつわるエピソードがとても印象に残っていて、確認のために再読。ホワイトハウスの近所に居を構える事で影響力を増していく事務局は、制度的関係よりも実際の政治では心理的関係が重要であることの実例でしょう。組織よりもコネの持つ実際的な力というのは、著者の裏テーマのようにも見えます。本書の主人公もそれを使ってのし上がったはずなのですが、モーレツビジネスマンでクソ真面目なステイトマンだったこの人は制度的な部分に軸足を置くところが多すぎたのかもしれません。2014/09/29
-
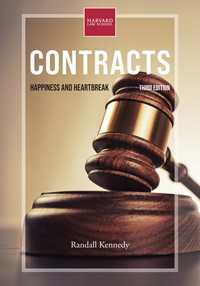
- 洋書電子書籍
-
契約ケースブック(第3版)
Co…




