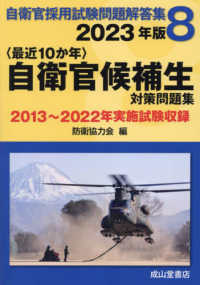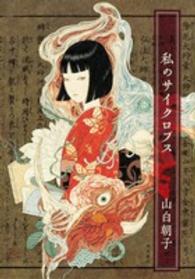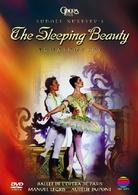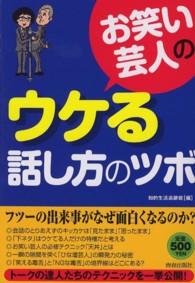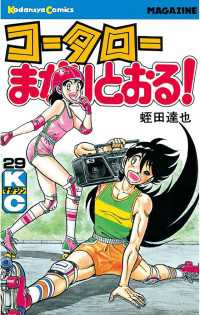内容説明
ヨーロッパ連合が結成され、国境線が事実上の意味を失いつつある現在、その進捗はドイツにどのような変化をもたらすのだろうか。ドイツの誕生から今日にいたる歴史に、「ドイツ的」とは何かを思索する。
目次
ドイツ史の始まり
叙任権闘争の時代
個人の誕生
神聖ローマ帝国
中世末期の苦悩
宗教改革の波
一五・一六世紀の文化と社会
領邦国家の時代
三十年戦争の結末
ゲーテの時代〔ほか〕
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
51
中世ドイツ史の碩学による平易な通史。特に中世~近世の文化や民衆の生活に関する記述は、簡潔ながら広い視野で描かれており、章末にある「間奏曲」というコラムもイメージの幅を広げるのに役立つ。でも最大の収穫はアジール。ドイツには中世以前から「聖域」としてのアジールがあり、そこに逃げ込んだものを庇護した歴史が脈々とある。本書が著された20余年前はドイツ統一、東ヨーロッパ変動期。そうした時代を考え、敢えて現代史のテーマをアジールに絞った著者の見識はさすがと言うしかない。20年後の今見て見事に現代的課題を捉えている。2019/10/26
もりやまたけよし
40
まとまりのない感じの書き方が原因なのか、読み進めるのに苦労しました。ドイツって混沌とした印象しか残りませんでした。これは通史として読むより、時代や地域を絞って読むしかないでしょうね。2020/11/04
ミカ
31
【図書館】ドイツの歴史を通史で読めたのはよかったけれど、私の場合もう少し基礎的な部分から学ばないとダメでした\(^o^)/2016/06/25
佐島楓
26
文化史や民俗史的な箇所を特に注目して読んだ。キリスト教と歴史を切り離せない関係に置いた国だと感じた。ヨーロッパでは特異な国のように書かれているが、そこまで考察できるようになるには周辺の国の歴史も知らねばならない。文化的な土壌はとても豊かで好きな国なので、理解を深めてゆきたい。2014/01/04
かふ
19
阿部謹也は『ハーメルンの笛吹き男』のような中世の民衆伝承の本で有名なのでそんな本を期待したが領主国家というような庶民よりも貴族性が全面に出るのだろうか。それがよくわかるのがゲーテの時代てビルドゥング・ロマン(成長物語)という精神主義が中心となるのはドイツ精神はそんな流れだと思ったのはドイツロマン派の詩を読んで感じたのだが、ベートーヴェンとシューベルトの違いがドイツ精神とメルヘンの精神の違いというような(コラムが面白かった)。それはバッハの教会音楽とシューベルトのウィーンの違いとか。2025/10/20