出版社内容情報
動物のサイズが違うと機敏さが違い、寿命が違い、総じて時間の流れる速さが違ってくる。行動圏も生息密度も、サイズと一定の関係がある。ところが一生の間に心臓が打つ総数や体重あたりの総エネルギー使用量は、サイズによらず同じなのである。本書はサイズからの発想によって動物のデザインを発見し、その動物のよって立つ論理を人間に理解可能なものにする新しい生物学入門書であり、かつ人類の将来に貴重なヒントを提供する。
★本書は『書評空間 KINOKUNIYA BOOKLOG』にエントリーされています。
内容説明
動物のサイズが違うと機敏さが違い、寿命が違い、総じて時間の流れる速さが違ってくる。行動圏も生息密度も、サイズと一定の関係がある。ところが一生の間に心臓が打つ総数や体重あたりの総エネルギー使用量は、サイズによらず同じなのである。本書はサイズからの発想によって動物のデザインを発見し、その動物のよって立つ論理を人間に理解可能なものにする新しい生物学入門書であり、かつ人類の将来に貴重なヒントを提供する。
目次
第1章 動物のサイズと時間
第2章 サイズと進化
第3章 サイズとエネルギー消費量
第4章 食事量・生息密度・行動圏
第5章 走る・飛ぶ・泳ぐ
第6章 なぜ車輪動物がいないのか
第7章 小さな泳ぎ手
第8章 呼吸系や循環系はなぜ必要か
第9章 器官のサイズ
第10章 時間と空間
第11章 細胞のサイズと生物の建築法
第12章 昆虫―小サイズの達人
第13章 動かない動物たち
第14章 棘皮動物―ちょっとだけ動く動物
1 ~ 3件/全3件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ehirano1
189
『島の法則』がは特に興味深かったです。ヒトの場合はそれが当てはまらないのはなぜかと思索を巡らす一方で、ゲノム解析と併せて分析するとどんなことが分かるのかな?(もうわかっている?)などと思索に耽りながら、今知り得る限りの生物の合理性を楽しみました。2024/12/07
月讀命
156
「生物によって時間の感じ方が違うんじゃないか」こんなテーマの本です。結構、難しく3年かかって読破。全ての生物の鼓動数は、大きいサイズ(ゾウ)も小さいサイズ(ネズミ)も一定であり、鼓動回数と個体のサイズから計算して、人の寿命は40余年とのことである。生物学的に見れば、私はとっくに死んでいる年齢だ。今生きているのは、食物連鎖からの逸脱、農耕と貯蔵、医学や薬学の進歩、自然環境の改善等、諸先輩方の努力のおかげである。そのことに感謝するとともに、生きながらえさせられている我々は、未来の人類になにか貢献すべきである。2012/09/10
まーくん
134
我が家のハムスター、ある日体重を量ってみたら63g。自分は63㎏。ちょうど1/1000!ハムスターの寿命ははかなく2,3年だそう。で、ハムスターの寿命3年、自分の寿命100歳と見積もれば(ちょっと無理か?)、寿命比は体重比のなんと1/2乗。もっともらしい。彼我の時間の流れは√1000で約30倍と妙に納得。でも本書を読むと寿命は体重の1/4乗に比例するらしい。当然、もっとしっかりした科学的根拠で論じています。他にもいろいろ興味深い事実・論証多数あり。ちなみに我が家のハムスターは2歳11か月で亡くなりました。2017/04/09
十川×三(とがわばつぞう)
113
面白い!哺乳類、鳥、昆虫、植物など、それぞれのサイズは必然。生物学者が分かりやすく解説。▼哺乳類の一生の心臓の拍動は20億回。生物により時間感覚が違う。昆虫の外殻をクチクラと呼ぶ。▼巻末、著者作詞作曲「一生のうた」の楽譜掲載。ユニークな先生だ!童謡テイスト。せっかくなのでコードつけてみた。(↓コメント欄へ)2021/09/30
absinthe
113
象もネズミも、それぞれの心臓の鼓動の間隔で割ってみるとその寿命は同じだと言う。つまり、生涯の心拍数は動物で共通なのだ。象は長生き、ネズミは早死にというのはあくまでも人間の眼鏡を通しての話。サイズはそれぞれ異なっても、実は共通の法則にしたがっている部分もいろいろあるのだ。
-
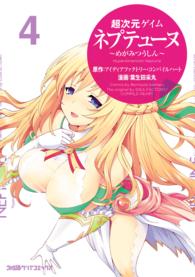
- 電子書籍
- 超次元ゲイムネプテューヌ~めがみつうし…




