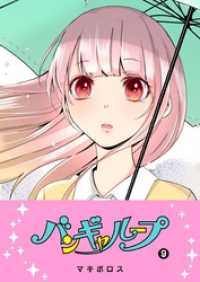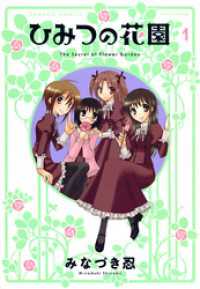内容説明
日本にワサビ、サンショウあればインドにカルダモンあり、フィリピンにショウガあればタイにはコブミカンあり。各国各民族それぞれに、食生活の重要な一角を担う植物がある。調理、染色、着香はもちろん、虫除け、入浴剤、装飾と用途はさらに広がる。ギリシア人の贅沢の再現から薬用資源としての可能性まで、植物成分の利用法を科学的に検証しつつ、生活に密着した香草薬草の世界を、熱帯アジアを中心に体験的につづる。
目次
葷菜の魅力―ニンニクとタマネギ
辛さの系譜―マスタードとワサビ
匂いづけさまざま―桜餅とレモングラス
着色も染色も―ライス・コーヒーとサフラン
燃える辛さ―トウガラシとココアのバラ
刺激を求めて―コショウとキンマ
芳香と辛味と―ショウガとカルダモン
木の葉の利用法―カレーの木とワサビの木
酸味野菜のはたらき―ライムとトマト
香りを食べる人たち―ハーブオムレツとオルガノ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
デビっちん
19
同じスパイスやハーブでも、各地に違った名前があるということから、それだけ多種多様な利用方法や古くからの歴史があるということがわかります。酸味や香り、辛さ、刺激、色といったように、香辛料の分類から展開型に話が進んでいました。香辛料の効能を科学的に解説したり、組み合わせを説いている点が参考になります。植物はあまり肥料をやらないほうが香りが強くなること、昔のヨーロッパではニンニクとタマネギを除くと、マスタードが一番よく使われた香辛料だったことに驚かされました。あの分類、展開型の論理で説明してみると?2016/07/20
こつ
13
様々なスパイスにハーブが出てきてお腹が空いてきます。色んな国で色んな食べ方をしていて食べてみたいものがたくさんできます。著者の方のチャレンジ精神がすごくて何でも食べてみるし工夫して現地のものを使いこなしているのでスーパー主婦ですね。ハルヴァこの間読んだ本にも出てきたけれどめちゃ美味しそうです。2021/10/21
澄
10
スパイス、ハーブ等を辛さ、匂い、色等の項目毎に紹介。知識欲を掻き立てられました。ただ、「民族学」というのは言い過ぎかな。。。 レモングラスを育てたくなった。2016/07/31
pollack
9
アジアを中心に、様々なスパイスやハーブの特徴とそれにまつわる食文化、そして成分の化学を、著者の豊富な経験を交えながら解説しています。ハーブやスパイスはそれぞれ独特の芳香を呈するがゆえに食文化を特徴付ける決め手となっている部分があり、著者がそれを目の当たりにして受けたカルチャーショックがよく伝わって面白かったです。文章も軽妙で引き込まれます。ただスパイスやハーブはとにかく多種多様で、馴染みのないものはとても伝わりにくいので、スケッチや写真が豊富だと随分良くなったろうに。惜しい。2016/10/04
東雲
7
アジアを中心に様々な香辛料について書かれた本。実際に現地で料理したり日本で栽培した体験なども書かれていて、古い本ではあるが内容は興味深い。同じ植物が海を越えた土地で似たような使われ方をしている事例などもあって面白い。ただ民族学とまではいかないか。成分や組織図なども数多く使われているが、如何せん難しい…。知らない香辛料が多いため図が多い方が良かったかもしれない。食べてみたい気持ちと旅行に行くのを躊躇う気持ちが半々。味は想像するしかないのだけど、思わず美味しそう!食べたい!って言った料理がいくつもありました2016/11/19