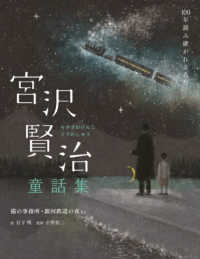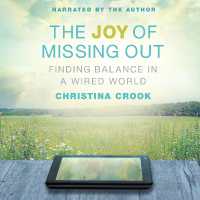- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 哲学・思想
- > 日本の哲学・思想(戦後思想)
出版社内容情報
戦後思想史の極点をなす哲学者と思想家の激しい論争を代表論考と対論によって再現する。解説=大澤真幸
【鶴見俊輔生誕100年/吉本隆明没後10年記念出版】
■目次■
【Ⅰ】根もとからの民主主義(鶴見)/自立の思想的拠点(吉本)
【Ⅱ】転向論(吉本)/転向論の展望(鶴見)
日本のナショナリズム(吉本)/吉本隆明(鶴見)
【対論】どこに思想の根拠をおくか/思想の流儀と原則
【解説】大澤真幸
内容説明
戦後思想史の極点へ。国家・大衆・ナショナリズムを問う。代表論考と対論三篇。
目次
1(根もとからの民主主義;自立の思想的拠点)
2(転向論;転向論の展望 吉本隆明・花田清輝;日本のナショナリズム;吉本隆明)
どこに思想の根拠をおくか
思想の流儀と原則
未来への手がかり
著者等紹介
鶴見俊輔[ツルミシュンスケ]
1922年東京生まれ。哲学者。42年、ハーヴァード大学哲学科卒局。46年5月、都留重人、鶴見和子、丸山眞男らとともに雑誌『思想の科学』を創刊。60年には市民グループ「声なき声の会」を創設、65年にはベ平連に参加した。主な著書に『アメリカ哲学』『限界芸術論』『戦時期日本の精神史』(大佛次郎賞)などがある。2015年死去
吉本隆明[ヨシモトタカアキ]
1924年東京生まれ。詩人・評論家。東京工業大学電気化学科卒業。52年『固有時との対話』で詩人として出発。その後、評論家として精力的に活動し、「戦後思想界の巨人」と呼ばれる。主な著書に『共同幻想論』『言語にとって美とはなにか』『最後の親鸞』『夏目漱石を読む』(小林秀雄賞)『吉本隆明全詩集』などがある。2012年死去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
ユ-スケ
takao
Meteor__Ready