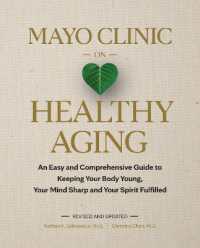- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 哲学・思想
- > 日本の哲学・思想(戦後思想)
出版社内容情報
日本思想の可能性とは何か。世界思想史の中で日本近代を捉え直した初の鶴見流日本思想案内。解説=長谷川宏
【鶴見俊輔生誕一〇〇年記念出版】
■目次■
【Ⅰ】日本思想の可能性/日本の思想百年/日本の思想用語
【Ⅱ】日本の折衷主義―新渡戸稲造論/日本思想の言語―小泉八雲論/石川三四郎/柳宗悦/ジャーナリズムの思想/平和の思想
【対談】普遍的原理の立場 丸山真男×鶴見俊輔
【解説】長谷川宏
内容説明
日本の近代をとらえなおす。田中正造から戦後の平和思想まで。
目次
1(日本思想の可能性;日本の思想百年;日本の思想用語)
2(日本の折衷主義 新渡戸稲造論;日本思想の言語 小泉八雲論;石川三四郎;柳宗悦;ジャーナリズムの思想;平和の思想)
普遍的原理の立場(丸山眞男×鶴見俊輔)
著者等紹介
鶴見俊輔[ツルミシュンスケ]
1922年東京生まれ。哲学者。42年、ハーヴァード大学哲学科卒業。46年5月、都留重人、鶴見和子、丸山眞男らとともに雑誌『思想の科学』を創刊。その後、京都大学、東京工業大学、同志社大学で教鞭をとった。60年には市民グループ「声なき声の会」を創設、65年にはベ平連に参加した。70年同志社大学教授を辞職。主な著書に『アメリカ哲学』『限界芸術論』『戦時期日本の精神史』(大佛次郎賞)『戦後日本の大衆文化史』などのほか『鶴見俊輔集』(全十七巻)、『鶴見俊輔座談』(全十巻)がある。2015年死去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
115
久し振りに鶴見俊輔さんとじっくりと向き合う。60~70年代の論文集だが古さはない。新渡戸稲造、田中正造、石川三四郎、柳宗悦などが語られている。「なぜ柳宗悦が私にとって大切な思想家かと言うと、彼が熱狂から遠い人だからである」で始まる柳宗悦論は秀逸。「愚俗の信」という言葉も心に刺さる。学者による高邁な平和論ではなく、素朴な日常生活上の信念に価値を置いた平和論への共感が民芸運動ともつながってくる。新渡戸さんに対し「その思想の中心は「やさしさ」」と語るが、鶴見さんこそ、やさしさと包容力の人である。いい読書だった。2022/08/30
1.3manen
55
思想を、人が自分の生活をすすめてゆくために考えるいっさいのこととして理解したい(27頁)。自由民権思想における中江兆民、北村透谷、キリスト教内村鑑三、社会主義幸徳秋水、堺利彦、山川均、尾崎秀実、無政府主義大杉栄、石川三四郎。国粋派と輸入派の中間で、土着派(28頁~)。同時代にふかく根ざす思想を求めるとき、田中正造(30頁)。新渡戸稲造によれば、修養とは、修身と養神を合わせてできた言葉で、二つの中心をもつ楕円形の意味領域(86頁)。新渡戸思想はやさしさ。あたたかみをもっている(117頁)。桐生悠々は名古屋で2022/09/03



![An EncyclopÃ]dia Ecclesiastica](../images/goods/../parts/goods-list/no-phooto.jpg)