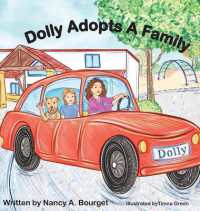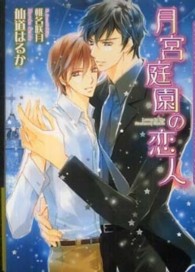出版社内容情報
19世紀の世界のピアノの技術の向上と同時に国産に情熱を傾けた山葉寅楠、独立した河合小市によりヤマハやカワイなどの日本の楽器メーカーが世界を席巻するまでに独自の発展を成し遂げた経緯を描く。
内容説明
山葉寅楠、国産への情熱。河合小市、独立への野心。19世紀に飛躍的に性能が向上する中で参入した国内の楽器メーカーが、試行錯誤を繰り返しながら世界を席巻するまでに独自の発展を成し遂げた経緯を描く。
目次
第1章 一九世紀のピアノ事情
第2章 ピアノ、日本に入る
第3章 国産ピアノ生産開始
第4章 大正時代
第5章 昭和戦前期
第6章 戦時下の楽器産業
第7章 戦後の再出発
第8章 急成長
第9章 一九八〇年以降
著者等紹介
井上さつき[イノウエサツキ]
愛知県立芸術大学音楽学部教授。慶應義塾大学、東京藝術大学、明治学院大学などで非常勤講師をつとめる。東京藝術大学音楽学部楽理科卒業。同大学院修了。論文博士(音楽学)。パリ・ソルボンヌ大学修士課程修了(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1959のコールマン
55
☆5。面白い。ピアノを取り巻く世界をあまねく記述している。出てくるネタがいずれも興味深い。1910年頃にアメリカの楽器業界誌「ザ・プレスト」で大々的に展開された日本のピアノ・オルガン業界に対するバッシング記事とか、夏目漱石がいやいやながらピアノを購入したとか、ヤマハが軍需用のプロペラをつくっていたとか、世界恐慌時、欧米のピアノ産業が大きく衰退したのに、日本ではピアノの売り上げは落ち込まなかったとか、第二次世界大戦ではアメリカでもピアノ製造が禁止されていたとか、とにかくページをめくる手がもどかしい。推薦本。2020/07/15
trazom
54
とてもいい本だ。国内外のピアノ産業がよくわかる。ピアノ製造がアメリカ一人勝ちに至る道筋、山葉寅楠と鈴木政吉の関係、ヤマハとカワイの鍔迫り合い、ヤマハと三木楽器の関係など、臨場感のある近代史である。何より驚くのは、学習指導要領に「器楽教育の重点化」「鍵盤楽器の指導」が書込まれたことが、文部省という権力を背景とした爆発的な需要の創造に繋がったという事実である。政商的な不透明感は拭えないが、それでも、自ら「音楽教室」を運営するなど、ソフト・ハード合わせた独特のビジネスを確立した日本の二大メーカーは立派だと思う。2020/03/18
koji
24
読友さんの書評で興味を持ち読みました。産業史は好きで割りと読むほうです。日本の産業発展の特色を私なりに纏めると①起業家の日本製に拘る情熱と野心、②それを支えるスタッフ・従業員の献身と勤勉さ、③必ず訪れる苦難(災害、人的対立等)を乗り越える不屈の精神力と運、④官民あげての産業育成、⑤時代の波になります。これを本書に引き合わせると、ヤマハ、カワイの歴史はぴたりはまります。著者は多数の文献にあたり、欧米比較、周辺産業(特にミュージックワイヤーの項は感動的)への目配せも十分に行い一級の価値をもつ文献に仕上げました2020/07/23
ジャズクラ本
17
◎ピアノの近代史をよくぞここまで調べたものだと感心させられる素晴らしい本だった。著名なピアニストは勿論のこと、シーボルトや漱石も登場する。日本においてはやはりヤマハとカワイが中心となるが、今となっては反則としか思えない攻防がある一方、経営者同士、技術者同士の交流があったりと良き好敵手の関係が窺える。安永徹がベルリンフィルのコンサートマスターに就任した1980年頃、ピアノ界では各コンクールの公式ピアノに日本製品が採択されるようになり、日本人としてとても誇らしく感じられたものだった。非常に楽しい読書でした。2020/08/28
ソバージュ
9
宝石商の山葉寅楠がオルガン修理を頼まれたことがきっかけで国産ピアノ生産が始まり、世界のコンクール使用のピアノが作られるまでの紆余曲折、ヤマハ対カワイ、学習指導要領の改定でピアノ売上数が倍増、シゲルカワイモデルの誕生秘話など、興味深い事ばかりで誠に面白かった!海外でヤマハ音楽教室の看板を見た際には驚いたが音楽教室の世界進出についてはもっと知りたかった。漆塗り蒔絵装飾の国産初ピアノも目にしてみたい。2021/01/20
-
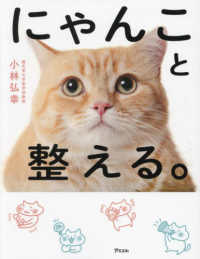
- 和書
- にゃんこと整える。