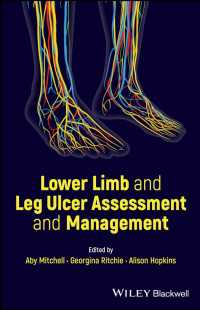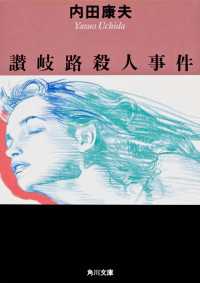出版社内容情報
★指揮者 大友直人、初の著書!
小澤征爾に胸ぐらをつかまれ、
バーンシュタインの嘲笑を浴びた若き日のこと。
世界に背を向け、日本で活動し続けた理由、クラシックは興行であるという原点に立ち返る意味を
自問自答し続けた日々を、余すことなく書ききった。
クラシックとはなにか、指揮者とはなにかを突き詰めた渾身の書下ろし。
なにが、世界だ! なにが、芸術だ!
いまこの目の前の観客に感動を与えられなくて、
なんの公演なのだろう。
興行としての原点を忘れたから、
クラシックは魅力を失ったのではないか……。
■第一章 「河原乞食」への道
指揮者を目指す
■第二章 「世界」がなんだ!
主戦場は日本と決める
■第三章 躍る沖縄市民
琉球で考えたこと
■第四章 子どもたちを育てる
■第五章 クラシックだけじゃない
音楽の魅力
■第六章 これからのクラシック
内容説明
小澤征爾に胸ぐらをつかまれ、バーンスタインに日本のオケを嘲笑された若き日のこと。世界に背を向け、日本で活動し続けた理由、クラシックは興行であるという原点に立ち返る意味を自問自答し続けた日々を余すことなく書ききった。音楽とはなにか、クラシックとはなにか、指揮者とはなにかを突き詰めた渾身の書き下ろし。
目次
第1章 「音楽家を目指す」と宣言する
第2章 「世界」がなんだ!―主戦場は日本と決める
第3章 踊る沖縄市民―琉球で考えたこと
第4章 子どもたちを育てる
第5章 クラシックだけじゃない―音楽の魅力
第6章 これからのクラシック
対談 クラシックの未来(片山杜秀×大友直人)
著者等紹介
大友直人[オオトモナオト]
指揮者。1958年東京生まれ。桐朋学園大学を卒業。指揮を小澤征爾、秋山和慶、尾高忠明、岡部守弘各氏に師事した。タングルウッド音楽祭において、A.プレヴィン、L.バーンスタイン、I.マルケヴィッチからも指導を受ける。桐朋学園大学在学中からNHK交響楽団の指揮研究員となり、22歳で楽団推薦により同団を指揮してデビュー。以来、国内の主要オーケストラに定期的に客演する。日本フィルハーモニー交響楽団正指揮者、大阪フィルハーモニー交響楽団専属指揮者、東京交響楽団常任指揮者、京都市交響楽団常任指揮者兼アーティスティック・アドバイザー、群馬交響楽団音楽監督を経て現在東京交響楽団名誉客演指揮者、京都市交響楽団桂冠指揮者、琉球交響楽団音楽監督。また、2004年から8年間にわたり、東京文化会館の初代音楽監督を務めた。第8回渡邉暁雄音楽基金音楽賞、第7回齋藤秀雄メモリアル基金賞を受賞。大阪芸術大学教授、京都市立芸術大学客員教授、洗足学園音楽大学客員教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
Isamash
ふじ
DEE
Susumu Kobayashi