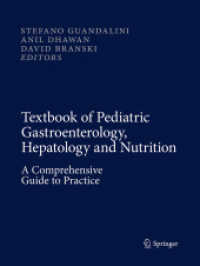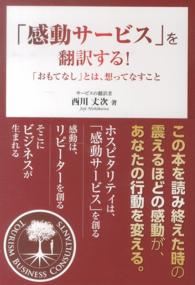出版社内容情報
将門という男は、なぜかくも激しく不器用なのだ!
音楽に取り憑かれ、「至誠の声」を求め旅に出た仁和寺の僧・寛朝。
荒ぶる坂東の地で出会ったのは、古き法に背き、ならず者と謗られる人物だった――。
土豪、傀儡女、群盗……やがて来たる武士の世を前に、混迷を生きる東国の人々。
その野卑にして不羈な生き様に接し、都人はどんな音を見出すのか。
父に疎まれ、梵唄の才で見返そうとする寛朝
逆賊と呼ばれても、配下を守ろうとする将門
下人の身にして、幻の琵琶を手にせんと策略を巡らす千歳
「至誠の楽人」の名声を捨て、都から突然姿を消した是緒
己の道を貫かんともがく男たちの衝突、東西の邂逅を、
『若冲』『火定』の俊英が壮大なスケールで描き出す!
内容説明
野太い喊声、弓箭の高鳴り、馬の嘶き…血の色の花咲く戦場に、なぜかくも心震わせる至誠の音が生まれるのか!己の音楽を究めんと、幻の師を追い京から東国へ下った寛朝。そこで彼は、荒ぶる地の化身のようなもののふに出会う。―「坂東のならず者」を誰より理解したのは、後の大僧正その人だった。謀叛人・平将門と、仁和寺の梵唄僧・寛朝。男たちの魂の咆哮が響き合う歴史雄篇。俊英が描く武士の世の胎動!
著者等紹介
澤田瞳子[サワダトウコ]
1977年京都市生まれ。同志社大学文学部文化史学専攻卒業、同大学院博士課程前期修了。専攻は奈良時代仏教制度及び、正倉院文書の研究。2010年『孤鷹の天』で小説家デビュー。同作により第17回中山義秀文学賞を最年少受賞。13年『満つる月の如し』で第2回本屋が選ぶ時代小説大賞ならびに第32回新田次郎文学賞を受賞。近年の著書に『若冲』(第9回親鸞賞受賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
starbro
ウッディ
修一朗
あさひ@WAKABA NO MIDORI TO...
真理そら