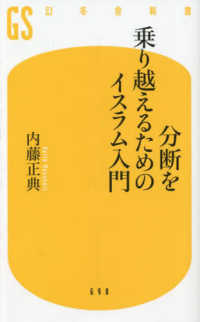出版社内容情報
「作戦」とは戦略とも戦術とも異なる、両者をつなぐ概念であり、現在、軍事専門家に最も重視される位置にある。この言葉を最初に現代戦に持ち込んだのはヘルムート・モルトケで、用語として使用されるようになったのは、比較的新しい。「作戦」の起源からその歴史をたどったうえで、現在論議されている主要な「作戦」の三事例を取り上げ、意義と特性を考察する。
序論 ポスト冷戦時代における「作戦」の特色―「軍隊行動の三レベル」
第一部 「作戦」の起源
第1章 「作戦」のない軍隊運用―絶対君主時代の戦闘回避主義
第2章 「大戦術」の開発とナポレオン戦争
第3章 ジョミニとアメリカ南北戦争
第4章 クラウゼヴィッツの戦略とモルトケの「作戦」
第二部 冷戦期までの「作戦」
第5章 米軍の消耗戦方式―封印された「作戦」の概念
第6章 ソ連軍の縦深「作戦」
第7章 フラーとハートの士気喪失「作戦」
第三部 ポスト冷戦時代の「作戦」
第8章 「緊要で、脆弱な『重心』」の追求
第9章 「影響」重視の考え方
第10章 複雑な「問題」と「システミック『作戦』デザイン」
おわりに
注
用語解説
中村好寿[ナカムラヨシトシ]
著・文・その他
内容説明
近代以降、戦略と戦術をつなぐ位置に「作戦」という階層が創出された。その起源と展開を歴史的に概観し、現在論議される主要事例を紹介する。いまや戦略・戦術より重視されるその概念とは。
目次
序論 ポスト冷戦時代における作戦の特色―「軍隊行動の三レベル」
第1部 作戦の起源(作戦のない軍隊運用―絶対君主時代の戦闘回避主義;大戦術の開発とナポレオン戦争;ジョミニとアメリカ南北戦争 ほか)
第2部 冷戦期までの作戦(米軍の消耗戦方式―封印された作戦の概念;ソ連軍の縦深作戦;フラーとリデル・ハートの士気喪失作戦)
第3部 ポスト冷戦時代の作戦(「緊要で、脆弱な『重心』」の追求;「影響」重視の考え方;複雑な「問題」と「システミック作戦デザイン」)
著者等紹介
中村好寿[ナカムラヨシヒサ]
1943年、広島県三次市に生まれる。防衛大学校卒業、スタンフォード大学に学ぶ。防衛大学校助教授、米海軍大学院客員講師、米国防大学客員研究員、陸上自衛隊東北方面総監部幕僚、陸上自衛隊幹部学校戦略教官、ジョージア工科大学客員教授、防衛研究所主任研究員を経て退官。宮城大学、防衛研究所、統合幕僚学校、航空自衛隊幹部学校等にて非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
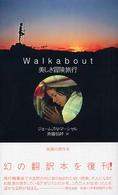
- 和書
- 美しき冒険旅行