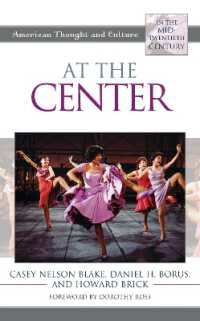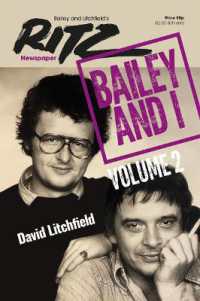内容説明
民主主義と自由主義は両立するのか。現代政治学の焦点の一つから、今日的な「政治」の意味が浮かび上がる。すべてが「資本」として流動化していく世界で、いかに資本主義と折り合いをつけ、どのように公共世界と私有財産を構築・維持していくか。これが「リベラルな共和主義」にとっての基本課題である。本書では、考察に必要な概念や論点に、歴史的・理論的な吟味を加える。まずは、フーコーとアレントの理論を足がかりに、そして、経済学、社会学の最新の知見を踏まえながら、実感の伴う政治の理解を目指す。
目次
第1章 政治権力はどのように経験されるか
第2章 アレントの両義性
第3章 フーコーにとっての政治・権力・統治
第4章 自由とは何を意味するのか
第5章 市場と参加者のアイデンティティ
第6章 信用取引に潜在する破壊性
第7章 「市民」の普遍化
第8章 リベラルな共和主義と宗教
第9章 リベラルな共和主義の可能性
第10章 政治の場
著者等紹介
稲葉振一郎[イナバシンイチロウ]
1963年、東京生まれ。明治学院大学教授。1986年、一橋大学社会学部卒、1992年、東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。岡山大学経済学部助教授、明治学院大学社会学部助教授等を経て現職。専門は、社会科学基礎論、社会倫理学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うえ
8
「ルソーは、ホッブズ、ロックとは異なり政治原理としての民主主義をはっりきと択んだが…ロックのそれよりもずっと時代錯誤的な印象を我々に与えてしまう…ルソーの民主国家の規模は、当時既にヨーロッパにおける相場となりつつあった主権国家のそれを下回り、古典古代的な都市国家のそれに等しい…第二に、百歩譲って古典古代のポリスをモデルにすることを許容したとしても、ルソーが好むのは世俗的な商業としてのアテナイよりも、都市というよりも収容所に近い、兵営国家スパルタであって…ホッブズ、ロックの構想とは正反対のものである。」2022/04/03
バーニング
3
議論は非常に難しいが、『新自由主義の妖怪』を経由するとまだ読みやすいかなと思う。アーレントやフーコーや、あるいはスミスから遠く離れてリベラルな共和主義を構想することの現代的意義とはなにか。経済学の一ジャンルとしての政治経済学とはどのようなものか。そもそも「政治」の範囲はどこからどこまでなのぁ、など。そうかハーバーマスもマルクス主義の枠組みからは逃れられなかったんだな、というのは勉強になった。 https://medium.com/p/7df09b7843112018/11/03
Kai Kajitani
3
この本のレビューをブログに書きました。http://d.hatena.ne.jp/kaikaji/201708282017/08/27
takeshi3017
2
稲葉氏の本は『社会学入門』『経済学という教養』に続いて3作目だが、本書は前2作よりも難易度が高い気がした。(とはいえ最後に読んだのが9年前なのでその記憶もあまり定かではないが…。)正直言ってとりあえず読んだ、という感じ。作者もそれは気にしていてあとがきによれば『社会学入門』『経済学という教養』と本書で入門書3部作にする予定が、今作は失敗した、と書いてある。入門書として書くのに失敗したので新書から叢書にレーベルを移した、とも。とりあえず作者の書いたうちで最も印象に残った文章をあげると、終わりの方で→2024/09/03
こややし
2
「経済学という教養」「社会学入門」の政治理論、政治哲学版。リベラルデモクラシーの擁護から、一歩進めて、あり得べき「政治」として、無産者においても、長期的な財産形成を支援するため、(強力な)再分配も行って、万人を有産者市民とする、「リベラルな共和主義」が展望される。アレント、フーコーの使い方やドゥルーズ・ガタリの使い方とその批判を面白く読んだ。しかし、この無産者へのフローだけじゃない、ストック形成にまで及ぶ再分配って、かなり過激で、ある種の「革命」ではないか。稲葉さんからの人民戦線への呼びかけとも読めた。2017/01/30