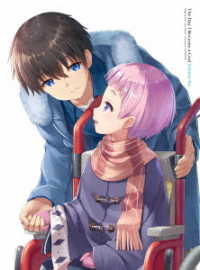内容説明
日本列島において十二支動物は、千数百年にわたって時間や方位の把握に用いられてきた。十二支の時空のシステムは数字の反復や積算ではなく、玄妙に変化する地球、太陽、月などの自然と、生きものや人の関係として展開してきた。列島に伝承された神話、物語、民俗、宗教などを考察し、個性あふれる十二支動物を導き手として、生きとし生けるものが織りなす時空へと分け入れば、その旅の先に豊かな文化の姿が装いを新たに立ち現れるだろう。広く関連諸学の成果を摂取して、現代文明がはらむ課題を乗り越えようと企図した画期的な日本文化論。
目次
第1部 生きとし生けるものの時空(生きとし生けるもの;五つの存在;存在から時間へ ほか)
第2部 十二支動物と日本文化の時空の旅―未来への伝統、過去なる近代、現在する物語(子 小さな宇宙;丑 大きな力;寅 強靱な真実 ほか)
第3部 よみがえる時空と文化学(十二支の潜在力;世界の文化へ―未来の十二支;文化学への関心 ほか)
著者等紹介
濱田陽[ハマダヨウ]
1968年生まれ。文化学者。京都大学法学部卒、京都大学大学院人間・環境学研究科文化・地域環境学専攻で博士号を取得。マギル大学宗教学部客員研究員、国際日本文化研究センター講師等を歴任し、帝京大学文学部准教授。法政大学国際日本学研究所客員所員等(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まりお
44
干支、十二支について。古事記や日本書紀などの神話、神社、人の階級ごとにどんな文化が広がっていたか、それらを紹介。面白かったのは十二支の動物が良い人を助け、悪い人を懲らしめる、在り来たりな話。十二支について説明する場面で良く見かけ、神聖さ、それに伴うありがたみがそれぞれ必ずあった。2017/03/30
魚京童!
14
面白い!読み切れないのが残念ではあるが、拾い読みしただけで伝わるこの面白さ。南方熊楠が同じ本を書いてた。そりゃー面白いよね。南方さんは表に出てこないけど、面白い人。なんだろうね。みんな誰かが言ったことしか見えなくて、視野が狭くなっている。盲人と象をやっている。でもそんなものなのかもしれない。見えるところが面白い。時間があっても読まないけど、時間がないと読まない本。これが教養なのかもしれない。閑暇って感じ。暇すぎて、暇すぎて、暇だから面白い。面白いのは面白い人は忙しいが、暇すぎても面白い人になる。中途半端は2023/02/25
うえ
8
「十二の意味群は…十二支動物を通して学んだ、この世界に関わる知恵を集約的に表している。 子 小さな宇宙/丑 大きな力/寅 強靭な真実/卯 弱さの希望/辰 想う、自然の聖霊/巳 実をはかる生きた尺度/午 近しい神の乗り物/未 遠いあこがれ/申 群れの誇り高い自由/酉 個の、恋するプライド/戌 伴侶力/亥 独りで出会う野生」「十二支月を四季に分ける場合、春が寅卯辰、夏が巳午未、秋が申酉戌、冬が、亥子丑に当たるとされてきた。他方、陰陽五行説は、春と夏を陽の木火、秋と冬を陰の金水とし…陽と陰の巡りとしてとらえる」2020/12/14
たま
1
十二支それぞれについて時間と文化をテーマに、様々な観点から日本人とどう関わってきたのかという考察。かつての日本人にとって、1番ファンタジーな動物は辰かと思いきや、実は羊。竜は沢山の伝承が残っており、そういう意味では馴染み深い存在。羊は日本にいないし、伝承もほとんどないし、名前の由来は未の刻が日の辻の時刻(14時位)に当たるからという無機質な理由ということで、竜よりも馴染みのない存在だったらしい。十二支以外の他の動物についても日本人との関わりを知りたいと思える位に面白かった。2023/09/14
MSTR
0
○「強の寅に対する弱の卯うさぎ」うさぎ―月―かぐや姫―因幡の白兎、そこに流れる共通なものや、「近の午に対する遠の未ひつじ」日本には居なかったものから異国へのあこがれ、素晴らしいものに付く未の字、等々、専門書としての他【ウンチク本の楽しみ】もある。 ○小の子-大の丑/強の寅-弱の卯/想の辰-実の巳/近の午-遠の未/群の申-個の酉/伴の戌-孤の亥; この対比の構成から、天地の流転を知る歴や方位の知識のみだった十二支観に、新たな興味を持たせてくれ、自分の干支だけでも、200字の感想を書けそうだ。2022/01/16
-

- 電子書籍
- レアモンスター?それ、ただの害虫ですよ…