内容説明
喜望峰ルートを開拓したポルトガルは、香辛料貿易の独占を狙い、インド洋沿岸に大規模な拠点を築く。大航海時代の幕が開け、日本を巻き込むグローバリゼーションの到来と抗争を描く。栄光と衰退の歴史を豊富な図版とデータにより検証。
目次
第1章 ヴァスコ・ダ・ガマとアジアへの海路
第2章 十五世紀のインドと東南アジア
第3章 ポルトガル人来航以前におけるアジアの域内交易
第4章 ポルトガルの制海権と交易独占
第5章 エスタード・ダ・インディアの発展と構造
第6章 アジアの交易におけるポルトガル人
第7章 喜望峰ルートと「胡椒王」
第8章 南アジアと東南アジア―ヨーロッパの交易パートナーか、外縁か
著者等紹介
フェルトバウアー,ペーター[フェルトバウアー,ペーター] [Feldbauer,Peter]
1945年生まれ。ウィーン大学歴史学科特任教授。自国の経済史および社会史の研究から出発、1980年発表の論文『Kinderelendin Wien(ウィーンにおける子供の悲惨)』により注目を浴びる。その後はグローバルな歴史の研究に転じ、欧米中心主義を脱却した歴史観を展開した
藤川芳朗[フジカワヨシロウ]
1944年愛知県生まれ。横浜市立大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
人生ゴルディアス
2
オスマン・トルコの本に、ホルムズあたりでポルトガルと争っていたという記述が確かにあった。しかしリスボンから香料諸島まで続くポルトガルが築いていた「要塞」ってなに? という疑問は常にあった。現代の感覚で言うと交易の拠点である海岸に要塞があるということは、その国を軍事的に支配(あるいは優越)しているのだという先入観がある。だが実際は、当時は大国は得てして内陸の農業を支配している国であった。しかもポルトガルは領土支配をもくろんだわけではないので、全面戦争にいたらなかった、ということのようだ。2016/09/19
ピオリーヌ
1
今までぼんやりとしか知らなかった、ポルトガルのアジア支配について知見を得られた。胡椒、クローブ等の流通量に関する具体的数値など、興味深い。2018/09/29
kentake
0
バスコ・ダ・ガマにより発見された喜望峰ルートによるポルトガルのアジア交易の歴史的意義について論じた本。エスタード・ダ・インディアと呼ばれるポルトガルによるアジア支配システムの繁栄が、必ずしもリスボンの意向に沿ったものではなく、現地主導のシステムによって成り立っていたという点は興味深い。2016/10/11
こなた
0
信長があと15年生きていたら、どんな世界になったかと、夢を馳せて読みました。ヨーロパ人は拠点作りが上手いですね。ギリシャ、ローマ以来の伝統ですね。2016/08/21
-
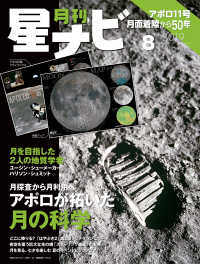
- 電子書籍
- 月刊星ナビ 2019年8月号 星ナビ
-
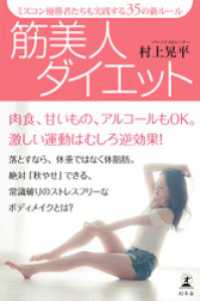
- 電子書籍
- ミスコン優勝者たちも実践する35の新ル…







