内容説明
三味線職人からヴァイオリン製作に目覚め、独学で世界的評価を受ける名器を作り上げ、輸出するまでに至った栄光の軌跡を、近代化による洋楽の普及と発展を交えながら辿る初の本格的評伝。
目次
第1部 明治編(生い立ち;ヴァイオリン第一号製作まで;ヴァイオリン作りを本業に ほか)
第2部 大正編(大正初期;ヴァイオリンの普及;第一次世界大戦時の輸出ブーム ほか)
第3部 昭和編(昭和初年の栄誉;懸命の努力;子どものためのヴァイオリン ほか)
著者等紹介
井上さつき[イノウエサツキ]
東京藝術大学音楽学部楽理科卒業。同大学院博士課程満期退学。論文博士(音楽学)。修士課程在学中にフランス留学。パリ=ソルボンヌ大学修士課程修了。現在、愛知県立芸術大学音楽学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひえやす
7
スズキバイオリンの創業者、鈴木政吉の自伝書。それは戦争や不況、バイオリンブームなど時代の波に翻弄された工業製品としてみた日本のバイオリン史でもあり、綿密な調査による裏付けは読んでいてとかく興味深い。舶来品信仰のためか国内での評価は量産品といったイメージで低かったらしいが、鈴木政吉自身の作った作品は、アインシュタインも絶賛し、海外のプロバイオリニストからストラディバリウスにも劣らぬ名器と絶賛されていた。明治から始まった国産バイオリン製造が僅か半世紀足らずでこれ程まで評価されていたとは知らなかったなぁ。。2015/07/27
黒豆
4
外観を見ただけで、木材,ニス,弦の選定から乾燥、組立て、そして量産化までよく立上げたものと思った。鈴木氏の手作業で氏が亡くなり作れなくなったものと思って読み始めたが、工業化し量産体制を構築しており、それがかえって付加価値を一段下に見られ、誰でも演奏出来ないこと、レコードの普及で買われなくなったようだ。大正前後の音楽普及には役立ったのかな?2014/07/09
Uzundk
3
日本に居るのであれば当然その音色は普段から聞く機会は多いだろうし、有名な演奏家も居て、少し大きな楽器店にいけば日本製の高級なバイオリンが見つけられる。しかし130年前の明治の中頃は限られた人にしか手に入らない船来の高級品であった。そんな西洋の楽器が日本でどう受容されて流行ったのか、どのようにして一般に手に入るようになったのか。華やかな表舞台の裏側、日本でそれらを作る事に人生をかけた人の話。彼らがなければ今の弾き手も居なかったと考えると演奏者達の親とも言える。2015/01/04
ジャッキー
2
鈴木バイオリンの創始者の鈴木政吉氏の三男がスズキ・メソードの鎮一氏。元々武士で、三味線等を内職で作っていた政吉氏が見よう見まねでヴァイオリンを作る。手に入る材料でヴァイオリンを作ったり、ヴァイオリン作成用の機械を作り出し、量産化に成功したりと経営者というよりも技術者。表紙に政吉氏が作った手工ヴァイオリンの写真が載っている。薄利多売を目指して大量生産をしてきた事もあって手工バイオリンは政吉氏晩年になってから。現在残っているのは戦争でも守り抜かれた物。2015/02/28
月華
1
図書館 2014年5月発行。研究成果の一部というのもあるのか、参考資料がかなりの量でした。鈴木のヴァイオリンは価値がないということで、残っているものを探すのも大変ということでした。中日新聞で鈴木のヴァイオリンの記事をみたことがあるような気がします。資料館で特別展が以前やっていたので、本を読んだ後に行ったら、より理解できたのではと思いました。2020/06/14
-
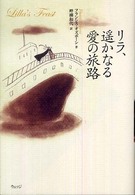
- 和書
- リラ、遥かなる愛の旅路




![先生スタイルバインダー Camel [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/44910/4491058695.jpg)



