内容説明
戦後社会では、さまざまな空間を革新勢力が席捲していった。しかしそうした雰囲気は、多分に焚きつけられ、煽られたものであった。誰が、どのように時代の気分を誘導したのだろうか。また、それはどのように、その後のねじれた結果をもたらしたのか。膨大な文献資料から聴き取り調査までを駆使し、今につながるその全貌に迫る。
目次
1章 悔恨共同体と無念共同体
2章 『世界』の時代
3章 進歩的教育学者たち
4章 旭丘中学校事件
5章 福田恆存の論文と戯曲の波紋
6章 小田実・ベ平連・全共闘
7章 知識人界の変容
終章 革新幻想の帰趨
著者等紹介
竹内洋[タケウチヨウ]
1942年(昭和17年)、新潟県に生まれる。京都大学教育学部卒業。同大学院教育学研究科博士後期課程単位取得満期退学。京都大学大学院教育学研究科教授などを経て、関西大学人間健康学部教授、京都大学名誉教授。専攻、歴史社会学、教育社会学。主な著書に『日本のメリトクラシー』(東京大学出版会、日経・経済図書文化賞受賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
36
戦後から七十年代までの左翼及び進歩的文化人の軌跡を追った一冊。昨今の左翼やマスコミ文化人が権威主義のくせに無頼ぶっていて気持ち悪いと感じていたが、その根っこが戦後直後まで遡れるとは思わなかった。というか現在でこそマルキシズムの破綻が明らかになっているが、当時は未来とは今よりも確実に良いものであるというマルキシズムもどきが学界、現実を問わず蔓延していた事を感じる。現実はさっさとその夢から醒めたけど、一部自称知識人等は未だ醒めていないように感じるなあ。戦後思想史としてもとりわけ興味深く読む事が出来た。2014/10/25
スズツキ
6
ある程度の知識は必要だが、若い世代の指定図書にしていいかも。当時の書物や大学生に対するアンケート(尊敬する人物に安部磯雄、長谷川如是閑、ムッソリーニなど)、政治、教育に関しての論文考察集。終章にあるオルテガの引用「大衆は喫茶店の会話から得られた結論を実社会に強制する」からの考証は切れ味鋭い。2014/05/11
のん
3
2011年出版。竹内洋の個人的な体験や経験についての話も多い。筆者は佐渡島で育ち、京都大学卒業後民間企業へ一旦就職するも、辞職し大学院へ進学。大学教授になった。1942年生まれの筆者が学生時代の頃には、言論界やキャンパス内は岩波朝日的な進歩的風潮が支配的であったようである。今日でも未だにその風潮は残っているように感じるが、当時よりは現在の方が「リアリスト」が増えているのではなかろうか。福田恆存を好意的に紹介するあたり、筆者は当時から進歩的文化人には思うところがあったのだろう。2025/08/31
ぽん教授(非実在系)
3
左翼でなければ知識人ではないという時代を覆っていた空気がいかにできて、最後どうなっていったか。一言で言えばそれについてを淡々と、著者の体験をも一次資料として利用しながら記述したものである。現在のモンスターペアレンツなどの原因たる革新幻想を憂慮する内容であり、パンとサーカスを求める民衆がローマを滅ぼしたように、革新幻想の子孫である進歩的コメンテーター・ニュースキャスター・芸能人といった人々の言説をそのまま受け取る大衆による反逆によって日本が衰退しないように、そのカラクリを暴いた本書は読んでよかっただけで終わ2012/07/24
OKB
2
序章のタイトルが「自分史としての戦後史」であるように、著者の生の実感に基づいた叙述であり、読書中は自分も20世紀日本の思想空間を生きている気分になる。人文学・社会科学に少しでも縁がある人なら誰でも面白く読めるポイントがあると思うので、そういう人におすすめしたい(文庫化されてます)。2020/09/22
-
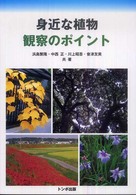
- 和書
- 身近な植物観察のポイント








