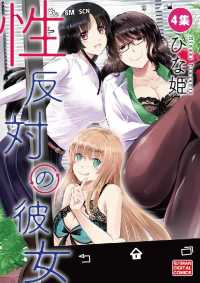内容説明
勝負師、研究者、芸術家の貌を併せ持ち、40歳の今も最高峰に立つ「考える人」。その真の強さとはいったい何か?10篇の「観賞」と「対話」が織り成す渾身の羽生善治論。
目次
はじめに 残酷な問いを胸に
第1章 大局観と棋風
第2章 コンピュータ将棋の遙か上をゆく
第3章 若者に立ちはだかる第一人者
第4章 研究競争のリアリティ
第5章 現代将棋における後手の本質
あとがき 誰にも最初はある
著者等紹介
梅田望夫[ウメダモチオ]
1960年生まれ。慶應義塾大学工学部卒業。東京大学大学院情報科学科修士課程修了。94年からシリコンバレー在住。97年にコンサルティング会社、ミューズ・アソシエイツを創業。『ウェブ進化論』『シリコンバレー精神』など著書多数。『シリコンバレーから将棋を観る羽生善治と現代』で第22回将棋ペンクラブ大賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
そり
14
「どうして羽生さんだけが、そんなに強いんですか?」とよくある質問に、著者はそうではないんだよとはじめに言う。私もそうだと思ってた。しかし、羽生さんは別格であることが読み進めるにつれてわかる。技術だけじゃない。タイトル戦で一年を通して緊迫した戦いが続く故に、羽生さんだけが得た勝負強さがあったんだ。対局相手の人間を見通して、敢えて最強の手を指さない。盤だけ見れば最善手でも、相手の研究背景も考慮すると最善でなくなるというのには衝撃を受けた。一般とプロとの差より一流と超一流との差の方が大きいというのも印象に残る。2013/05/31
緋莢
12
1996年、前人未到の七冠を達成。以後、激化する将棋の世界で最前線を走り続ける棋士・羽生善治。その真の強さとは一体何か?観戦記と対話から、その強さの秘密に迫っていく。 2017/01/09
macho
10
作者の翻訳能力が非常に高い。著作権のない研究成果が毎日泡のように出ては消える。そのような中で消えない泡や、粘りに粘ってから弾ける泡もある。その全てを残しておく必要性について論じているこの本は、AI時代到来の今だからこそ絶対に知っておかねばならない棋界の歴史本でしょうね。研究成果に著作権がないなんて、なんて斬新で残酷な世界なんだろう。しかして、人間の脳力の限界を知るボードゲームとして将棋は、素晴らしい2020/09/16
hitotoseno
10
本書は2009年の木村一基との間で行われた棋聖戦に始まり、翌年の深浦康市との間で行われた棋聖戦で終わる、約一年間羽生善治がどんな相手と指していたのか、どんな将棋を指していたのかを追跡するエッセイである。このころはまだ矢倉が主流で、特に急戦矢倉をどう指すのかが棋士の間のテーマだった。コンピュータソフトもまだまだひよっこ、そして羽生を脅かす存在となるのではないか、と言われている若い棋士に佐藤天彦や豊島将之の名が挙げられていない頃の話だ。このころから少なからず将棋を見ていた小生としてはやや懐かしい思いで読んだ。2018/08/02
向う岸
9
駒の動かし方も良く判っていないが、棋士や戦術の話は好き。天才・羽生善治ですらミスもするし、対戦相手のいる勝負事だから全てが思い通りに進んだりはしない。それでも勝ち続けるのは、定跡の研究、応用力、勝負師としての勘が総合的に高いレベルで備わっているから。一瞬の内にあらゆる手を考えて出た結論が「負け」だった時、棋士はどんな気持ちになるのだろう。将棋は新しい手がないか可能性を探る旅なんだな。2014/05/11