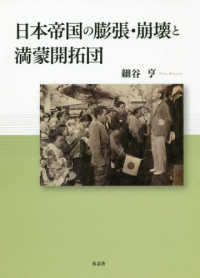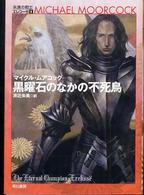目次
第1部 民族学者のまなざし(人類学のあらたな地平;ムスリム社会の「女性解放」;噂のなかのルクソール;イスラーム世界と「世俗化」;フィールドの「年齢」 ほか)
第2部 現代世界と人類学の転換(近代における「伝統」―歴史人類学へのひとつのアプローチ;フィールドワークと民族誌の現在―「マリノフスキー」から「オリエンタリズム」へ;価値の普遍性と個別性―「開発の価値」と「価値の開発」;女子割礼および/または女性性器切除(FGM)―一人類学者の所感
文明化と「価値の開発」―ターリバーンの「暴挙」と文明)
著者等紹介
大塚和夫[オオツカカズオ]
1949年、北海道生まれ。80年、東京都立大学大学院社会人類学専攻博士課程単位修得。国立民族学博物館助手、助教授、東京都立大学人文学部助教授を経て、現在、同教授。博士(社会人類学)。専攻は、社会人類学、中東民族誌学。エジプト、北スーダンなどアラブ・ムスリム世界を中心に人類学調査・研究をおこなう
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。