出版社内容情報
現代日本の混迷の奥底にある「教養」の衰退をどうすれば防ぐことが出来るのか。かつての「教養主義」の問題点を再検討しつつ、日本再生のための「新しい教養」の在り方を提示する。
内容説明
現代日本の混迷の奥底には「教養」の衰退という底流があることがようやく多くの人に悟られてきつつあるようだ。日本の再生のためには、「新しい教養」が築かれねばならない。それでは、それはどのようなものとなるのか。かつての「教養主義」のどこに問題があったのかを再検討。21世紀日本の「新しい教養」の有り方へのヒントを提供する一冊。
目次
1 総論
2 現代日本と新教養
3 再考・近代日本の教養
4 日本型「知識人」の肖像
5 大学像の変貌
6 新教養をめぐる対話
7 教養の誘惑
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
てれまこし
11
教養主義に影響された最後の世代の一員で、広い意味での京都学派人脈に連なる著者と、自分は多くの問題意識を共有してる。教養主義というのはエリート、戦前であればせいぜい1~5%の人びとの文化である。戦後に急激に高等教育が民主化されたときに、民衆がこの教養主義文化に同化されるよりも、逆に大衆文化や実利主義的文化が大学に持ち込まれる度合いの方がずっと強かった。それだけではなく、少数精鋭のエリートもやはり数の力に勝てずに大衆文化や役立つ実学志向の方に同化されたのである。そして教授陣と学生の間に埋めがたい距離が生じた。2021/05/29
いわたん
1
「新しい日本の教養」に続いて読了。読み応えあり。細川護立の3つの書斎、いいなあ。白洲正子との繋がりも初めて知った。 発行は2000年で、学生のデータなどは90年代終わり頃。今の大学の状況ではどうだろう。中学校の英語の教科書を使わざるを得ない大学がある状態で「大学での教養」というくくりが出来るか。しかし、医者や技術者、経営者を目指す学生向けに人文的教養を学ぶ時間は必要だと思う。一線に出れば忙しくなろうし、「今と違う事を考えたことがあったな」と振り返る時間があった方が良い。人ごとでは無いな。2011/11/08
katashin86
0
著者の教養についての小論、「教養人」との対談、書評の集成。刊行2000年以降も教養への社会的関心は引き続きあるものの、「新しい教養」の姿はまだ見えない。2021/01/15


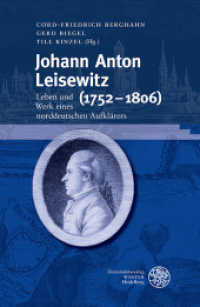


![別冊少年マガジン 2020年8月号 [2020年7月9日発売]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0876671.jpg)



