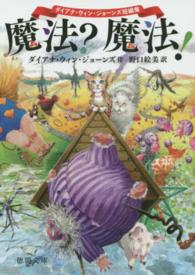出版社内容情報
歴史を俯瞰し、教養の意義を再定義。大ベストセラー『国家の品格』著者による独創的文化論。大ベストセラー『国家の品格』著者による独創的文化論。教養はどうしたら身につくのか。教養の歴史を概観し、その効用と限界を明らかにしつつ、数学者らしい独創的な視点で「現代に相応しい教養」のあり方を提言する。
藤原 正彦[フジワラ マサヒコ]
著・文・その他
内容説明
「教養」とは、世の中に溢れるいくつもの正しい「論理」の中から最適なものを選び出す「直感力」、そして「大局観」を与えてくれる力だ。では、教養を身につけるためにはどうしたら良いのか。教養の歴史を概観し、その効用と限界を明らかにしつつ、数学者らしい独創的な視点で「現代に相応しい教養」のあり方を提言する。大ベストセラー『国家の品格』の著者が放つ画期的教養論。
目次
第1章 教養はなぜ必要なのか
第2章 教養はどうやって守られてきたか
第3章 教養はなぜ衰退したのか
第4章 教養とヨーロッパ
第5章 教養と日本
第6章 国家と教養
著者等紹介
藤原正彦[フジワラマサヒコ]
1943(昭和18)年旧満州生まれ。数学者、理学博士、お茶の水女子大学名誉教授。東京大学理学部数学科卒、同大学院理学系研究科修士課程修了。父・新田次郎、母・藤原ていの次男(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Aya Murakami
126
図書館本。 各国家の教養情勢と教養はかならずしも世の中をよい方向に導くものではないということが書かれた本。ドイツとフランスそしてイギリスが仲が悪いというのは聞いていましたが、教養の世界でもおたがいマウントを取り合っているとは…。教養人があきれますね。そしてマウントを取り合っていたり日本のように舶来教養にかぶれている間に無知な大衆に担がれたポピュリストという絶対悪の攻撃にあい…。結構教養の世界ももろいものです。2022/03/25
rigmarole
64
印象度B+。ヨーロッパの教養とはギリシャ古典であるとか、日米戦争は強者であるアメリカが弱者である日本をいじめた結果であるとか、それなりに筋の通った説明ではあるものの一面的で偏っているようにも私には思われます。そのことに留意する必要があるでしょうが、教養という観点から論じた歴史解釈、国民性比較や日本の教養についての論考は、単純化しているとはいえためになります。そして、民主主義は扇動者に導かれた衆愚政治になる危険を孕んでいるので、国民に教養を要請する。ついては本を読め。これらについては、私は完全に同意します。2019/01/18
inami
58
◉読書 ★4 アメリカの意図を見抜けなかった日本は、90年代後半からバブル発生と崩壊の真因の分析をしないまま、バスに乗り遅れるなとばかりに「グローバル・スタンダード」というアメリカ型資本主義に引きずり込まれ資産を喪失。ヒットラーが教養市民層出身の幹部を片端から追放し暴走したドイツを例に→「教養なき国民による民主主義ほど怖いものはない」と警鐘を鳴らす。「教養」という座標軸がない論理は自己正当化に過ぎず、座標軸のない判断は根無し草のように頼りないもの・・と、自分は「教養」が極めて希薄につき、心に響きましたわ〜2019/01/03
future4227
54
超ざっくり言うと、民主主義国家を維持するには国民一人一人が高い教養を身につけなければならず、そのためにはいっぱい本を読めと。グローバリゼーションとか言って欧米文化ばかりを追っかけるな。日本の方が断然凄いんだぞと。とまあ、いつもの藤原節が炸裂。チャーチルを無能な政治家と言い切るあたりも気持ちいい。国家の繁栄や衰退と学問や教養との相関関係を世界史の流れを通して説明してくれるので大変勉強になった。「1日に1頁も本を読まない人間はケダモノと同じだ」という藤原先生の祖父様の言葉は強烈だけど頷ける。2019/11/14
aika
52
鋭くユニークに語られる、教養という視点から観た国家の歴史に釘付けです。かつてのドイツや日本の失敗から、教養とは一部のエリートのためのものではなく、広く国民がその責任を果たすために身につけるべきであるとの著者の主張に共感しました。日本人の情感に根付いて庶民に永らく愛されてきた「大衆文化」に着目し、教養とは陰に隠れて涙を流している人々の存在に目を向ける人格的な優しさに裏打ちされたものであることに得心しました。「本を読むということは、人間として生きること」この最後の一文が、沈み込むような重みを持って響きます。2019/11/04