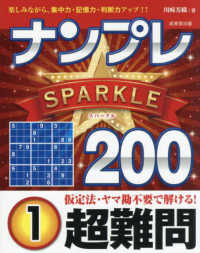出版社内容情報
親の言うことをよく聞く「いい子」こそ危ない! 矯正教育の知見で「子育ての常識」を覆す。
「明るさ」と「素直さ」の背後にあるものを見よ。「いい子」は危ない。自分の感情を表に出さず、親の期待する役割を演じ続け、無理を重ねているからだ――。矯正教育の知見で「子育ての常識」をひっくり返す。
内容説明
意外なことに、刑務所への出入りを繰り返す累犯受刑者には「いい子」だった者が多い。自分の感情を素直に出さず、幼少期から無理を重ね、親の期待する役割を演じることに耐えられなくなった時、積もり積もった否定的感情が「犯罪」という形で爆発するのだ。健全な子育ては、「いい子」を強いるのではなく「ありのままの姿」を認めることから始まる―。矯正教育の知見で「子育ての常識」をひっくり返す。
目次
第1章 明るく笑う「いい子」がなぜ罪を犯すのか
第2章 少年院に入ると、さらに悪くなる
第3章 受刑者の心の奥底にある幼少期の問題
第4章 「つらい過去」に蓋をしてはいけない
第5章 子どもの前に、親が自分自身を受け入れる
第6章 幼少期の子育てで知っておきたいこと
著者等紹介
岡本茂樹[オカモトシゲキ]
1958(昭和33)年兵庫県生まれ。元立命館大学産業社会学部教授。臨床教育学博士。大学での研究・教育活動の傍ら、刑務所での受刑者の更生支援にも携わる。2015年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
購入済の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ルピナスさん
85
私は笑顔が自分を救うと信じていたが、そもそも幼い頃、何故笑顔を作るようにしていたかを本書と共に掘り下げる過程は本当に苦しかった。私の場合は大丈夫という習慣がつき過ぎ、人に甘える事が出来るようになるまで相当時間がかかった。今は自分の家族という心の安らぎの場を得て犯罪とは縁がないと思いきれるが、作者からみたら危ういと思う段階もあったかもしれない。我が子が15歳になり自立も見えてきた今望むのは、育てやすいいい子ではなく、幸せである事。人は人によってしか癒されない。条件付きでない愛情をもって今日も接していきたい。2022/08/29
takaC
77
終いには結論も述べぬまま終わってしまった印象が残ったが、 著者の没後出版(享年57は随分と若死ですね)だったそうで、じゃあ仕方ないのかな。2017/05/13
鈴
48
「いい子」とは親にとって都合のいい子であり、子供本人は「いい子」を演じていて、自分の欲求を訴えられない。反抗期は「自己表現期」。わたしは反抗期もなかった「いい子」ちゃんだったけど、親の悲しむ姿を見たくないので、犯罪をする勇気はない。でも子供のときは、けっこう危うかったよなーと思う。今の息子より、子供時代の私の方が心配な子供で可哀想だったな。2017/05/06
テツ
36
ぼくはプライベートでも仕事でもいい子どころかまともに育てられもしなかったグレたこども達に接することが多いのでタイトルには若干の違和感があったけれど読み進めるうちに納得。その手のいわゆる軽挙妄動が過ぎるグレてしまった子たちとは異なる、抑圧されて溜め込みすぎていつか爆発してしまうかもしれない、良い子として育てられたこども達。やらかし方と踏み外し方が違うんだね。愛する相手への接し方はたった一つ。それはこどもに対しても同じ。「あなたの存在そのものを愛する」と伝え続けること。我慢ならずに作り変えるのは愛ではない。2019/12/08
ちさと
34
人格形成は幼少期で決まり、子供への抑圧はその心を歪ませる。自分の価値観が子供に伝わる可能性はとても高いし、親が固定観念に囚われた子育てをするのは危険だと、本書を読んで内省しました。ただ、ほとんどの親は真っ当な道を進んで欲しいと子育てに四苦八苦し、結果どんな方法でも子供は親に対して肯定的・否定的感情両方抱えるのが当たり前だと思う。大切な事を伝えるためにこのようなタイトルにしているのだと思いますが、その部分は懐疑的。前半はさらっと、後半をじっくりと読むことをお勧めします。2018/10/23